お知らせ
NEWS
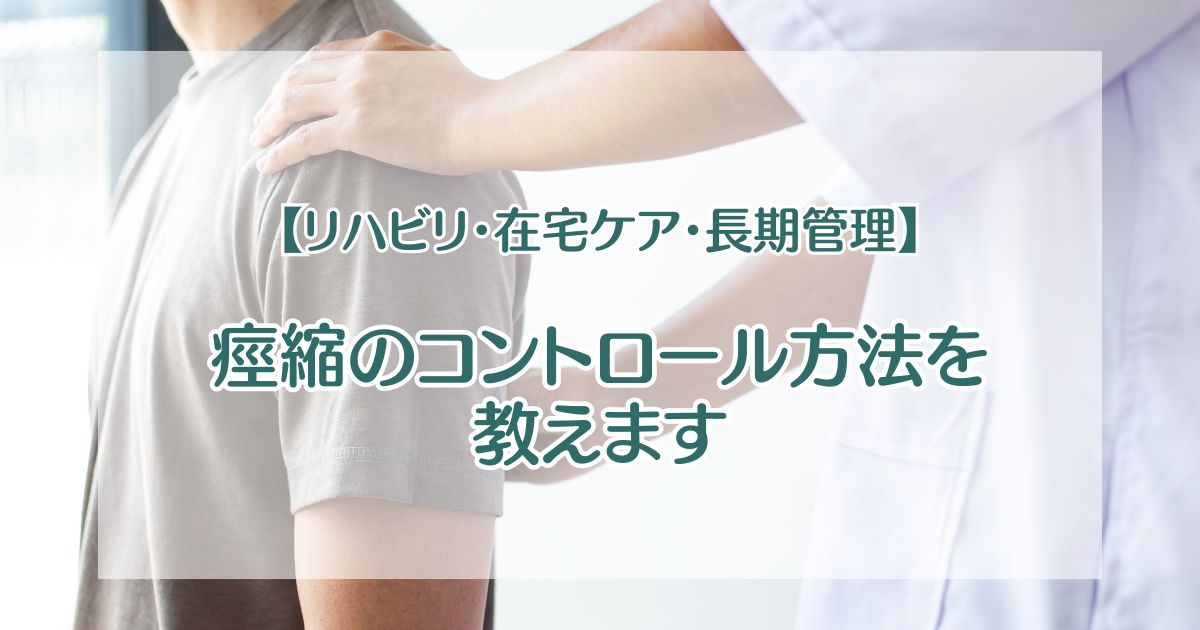

「痙縮による手足のこわばりがつらい…」とお悩みではありませんか?
放置すれば、痛みや生活動作の悪化につながる恐れもあります。
この記事では、症状の原因から自宅でのケア、自費リハビリの選び方まで解説します。
痙縮とは何か?【症状と原因の正しい理解】

この章では、痙縮の定義や原因、他の似た症状との違いを詳しく解説します。
「筋肉の緊張」とは
痙縮を正しく理解するためには、筋肉の緊張について理解する必要があります。
筋肉の緊張とは、筋肉が力を入れていない時でも、適度の張りや硬さを保っている状態の事を指し、医学的には「筋緊張」と呼ばれます。
筋緊張によって、意識していなくても姿勢を保つことができたり、いつでも動き出せるように準備をしている状態を作り出すことができます。
運動を行う場合には、筋肉が急激に伸びすぎるのを防いだり、スムーズに意図した動きを行ったり、姿勢を安定させたりする役割を果たします。
痙縮とは:医学的な定義と症状の特徴
痙縮とは、筋肉が過度に緊張しすぎて、硬くなる状態を指します。
痙縮は、主に脳卒中や脊髄損傷など、脳や脊髄といった中枢神経の障害によって起こります。
痙縮の主な症状は以下の通りです。
- 身体の筋肉が硬くなったように感じ伸びにくい
- 関節が動かしにくい
- 意図しないのに手足が動いてしまう
筋肉の過緊張によって痛みを感じる原因や部位によって症状の出方は異なります。
腕や手指では以下のような症状が見られます。
- 指が握ったままとなり、開きにくい
- 肘が曲がったまま伸びにくい
- 手首が内側に曲がって反らせることが難しい
- わきの下がつっぱり、手が上に上げにくい
足では以下のような症状が見られます。
- 足を床につくと踵が浮いてしまう
- つま先が内側を向いてしまう
- 足の指が曲がったままになる
- ももの内側がつっぱり外側に開きにくい
- 膝が曲げにくい
症状が軽い場合でも、放置せずリハビリを始めることが重要です。
痙縮の基本的なメカニズム
痙縮が発生するメカニズムは複雑で様々な要因が関連していると考えられています。
通常、私達の脳は筋肉の動きをコントロールするために、興奮性の信号と抑制性の信号の両方を脊髄に送っています。
痙縮と痙性麻痺・拘縮との違い
痙縮と混同されやすい言葉に「痙性麻痺」と「拘縮」があります。
それぞれには明確な違いがあります。
- 痙縮とは:筋肉の緊張が異常に高まり、手足が動かしにくくなったり勝手に動いてしまう状態
- 痙性麻痺とは:運動麻痺があり、痙縮が生じている状態
- 拘縮とは:関節を構成している筋肉、皮膚、腱などの軟部組織が不動などの影響で硬くなり、関節の動きが制限されてしまう状態
痙縮が日常生活に与える影響とは
痙縮があると、日常生活動作(ADL)に大きな影響が出ます。
- 衣類の着脱に時間がかかる
- 手すりや杖を使った移動が困難になる
- 箸やスプーンを持つことが難しくなる
生活の質(QOL)が低下する恐れがあります。
しかしながら、正しいリハビリを継続することで動作は改善できる可能性があります。
痙縮があるときの「痛み」「不安」「困りごと」
痙縮には「動きづらさ」だけでなく、心理的な不安や身体的な痛みが伴います。
- 筋肉のこわばりによる関節の痛み
- 「また動かなくなるのでは」という不安感
- 「リハビリを頑張っても意味がない」と感じる無力感
このような不安には、リハビリ専門職の継続的な関与が効果的です。
痙縮のコントロールの重要性

この章では、痙縮を適切にコントロールする必要性と、その背景にあるリスクや目的について解説します。
症状を放置した場合に生じる悪影響や、日常生活の質を守るための目標を明確にすることで、患者様やご家族様が前向きに取り組める基盤を作ります。
なぜコントロールが必要か?
痙縮は、時間の経過とともに進行しやすく、放置すれば関節や筋肉の柔軟性が低下します。
これにより歩行や着替え、食事動作などの生活動作が制限され、介助の必要性が高まります。
適切なコントロールは、症状の悪化を防ぎ、できる動作を維持するために不可欠です。
痙縮を軽減すれば、リハビリ効果が高まり、日常生活の自立度も向上します。
- 関節や筋肉の柔軟性を保てる
- 生活動作の制限を最小限に抑えられる
- リハビリ効果を最大限に引き出せる
放置のリスクと介助量の増加
痙縮を放置すると、筋肉の緊張が強まり、関節が硬くなる拘縮に進行します。
長期間、拘縮の状態が続くと元に戻すことが難しくなり、介助量が増加することで、ご家族様や介助者の負担が大きくなります。
さらに、歩行時のバランスが崩れ転倒リスクが高まるほか、長時間同じ姿勢を続けることで褥瘡(床ずれ)や血流障害も生じやすくなります。
こうした二次的な障害を防ぐためにも、早期のコントロールが重要です。
生活の質を維持・向上させるための目標
痙縮コントロールの最終的な目標は、患者様の生活の質(QOL)を守り、向上させることです。
具体的には、自分でできる動作を増やし、外出や趣味活動を継続できる状態を目指します。
リハビリや医療的アプローチを組み合わせることで、動作の改善だけでなく心理的な安定や社会参加の機会も広がります。
患者様ご本人とご家族様が安心して生活できる未来のために、日々の管理が欠かせません。
リハビリテーションでできること

この章では、痙縮のコントロールにおいてリハビリテーションが果たす役割と、その具体的な方法を解説します。
理学療法士や作業療法士が行うアプローチは、薬物療法や手術と異なり、副作用が少なく日常的に継続できる点が特徴です。患者様やご家族様が自宅でも実践しやすい方法を紹介します。
関節可動域訓練・ストレッチの実践方法
関節可動域訓練(ROM訓練)とは、関節の動く範囲を維持・拡大するための運動です。
痙縮が強まると関節が動かしにくくなり、拘縮のリスクが高まります。
定期的なストレッチは筋肉の柔軟性を保ち、緊張を和らげます。
実践のポイントは、無理のない範囲でゆっくりと伸ばすことです。
急な動きは筋緊張を増加させる可能性があるため避けます。
生活動作に直結するタスク指向型訓練
タスク指向型訓練とは、実際の生活動作を想定した運動練習です。
例えば着替えや食事、歩行など、日常で必要な動作を繰り返すことで脳と筋肉の連携を改善します。
この方法は、ただ筋肉を動かすだけでなく、「目的のある動き」として訓練するため、実生活での動作改善に直結します。
装具療法と姿勢管理の重要性
装具療法は、関節や筋肉の動きをサポートし、姿勢を安定させるために用います。
装具を適切に使用することで、歩行の安定や転倒予防が期待できます。
また、座位や立位での姿勢管理は、痙縮による不要な筋緊張を軽減します。
特に長時間同じ姿勢を続ける場合は、体圧分散や支持面の調整が効果的です。
振動刺激や温熱療法の役割
振動刺激療法は、特定の周波数で筋肉を刺激し、緊張を抑制する方法です。
温熱療法は血流を促進し、筋肉のこわばりを和らげます。
これらは単独でも効果がありますが、ストレッチや運動療法と組み合わせることで相乗効果が期待できます。
家庭でできるセルフケアと記録の方法
自宅で行うセルフケアは、リハビリの成果を維持するために重要です。
毎日のストレッチや姿勢の工夫、温熱療法などを生活に取り入れます。
- 1日1〜2回の軽いストレッチ
- 姿勢をこまめに変える
- 実施内容や変化を簡単に記録する
記録を続けることで、症状の変化や効果の有無を把握しやすくなります。
これにより、医療者との相談がより具体的かつ効果的になります。
自費リハビリを選ぶメリットとデメリット

自費リハビリには多くの利点があります。
ただし、すべての方にとって最適とは限りません。
ここでは、利用前に知っておくべき利点と注意点を整理します。
メリット|自由なプログラム設計と専門性の高さ
最大のメリットは「一人ひとりに合わせた支援が可能なこと」です。
保険内リハビリでは難しい、個別目標に基づいたリハビリ計画が立てられます。
専門職による継続的な評価と調整も魅力です。
- 運動機能だけでなく、社会復帰や趣味活動も支援
- 担当者が変わらないため、継続的な信頼関係が築けます
目標に向かって伴走してくれる存在が得られる点は大きな価値です。
メリット|回数・期間の制限なしで継続できる
保険制度では、リハビリの期限や上限があります。
それに対し、自費リハビリでは必要なだけ継続できるという利点があります。
そのため、効果の実感や維持がしやすくなります。
- 月1回〜週2回など、生活状況に合わせた頻度で通所可能
- 「回復の可能性が残っているのに終了」といった不安を回避
リハビリを「やめたくない」方には強い味方となります。
デメリット|費用負担と医師の関与がない不安
自費リハビリは全額自己負担です。
90分コースでは30,000円と高額な設定もあります。
↓↓↓詳しい料金相場については、こちらの記事をご覧ください。
【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!
医師との連携が心配な方は、診療情報提供書を持参しましょう。
かかりつけ医と連携する施設なら安心が高まります。
高額でも専門性と設備投資による付加価値が得られます。
デメリット|施設によって質に差がある
自費リハビリ施設は民間運営のため、提供サービスの質にバラつきがあります。
リハビリ職の資格保有者がいない施設や、エビデンスに基づかない内容も存在します。
以下の視点で選ぶことが重要です。
- 理学療法士・作業療法士など国家資格者が対応しているか
- 初回カウンセリングが丁寧かどうか
- 過去の改善事例が明示されているか
利用者の声や体験談を参考に、慎重に比較することをおすすめします。
「元気を取り戻せた」と実感する患者様が多いことも、自費リハビリの大きな魅力です。
↓↓↓脳神経リハビリセンターのお客様の声は、こちらのページでご確認いただけます。
脳神経リハビリセンターのご利用者様の声
継続的なコントロールのためにできること

この章では、痙縮を長期的に安定させるための取り組みを、患者様ご本人・ご家族様・地域や専門職の視点から解説します。
痙縮のコントロールは一度の治療で完結せず、日々の積み重ねと多職種の協力が欠かせません。
継続的な管理体制を整えることで、生活の質を守りやすくなります。
患者様ご本人が意識できる日々の工夫
日常生活の中での小さな工夫が、痙縮の悪化防止につながります。
無理なく続けられる習慣として取り入れることが重要です。
- 1日数回の軽いストレッチや関節運動
- 長時間同じ姿勢を避ける
- 疲労や寒冷環境を避ける
特に寒さやストレスは痙縮を強めやすいため、衣服や環境を工夫し、体を温めることが有効です。
ご家族様による見守りとサポートのコツ
ご家族様の適切な見守りは、患者様の安心感と安全性を高めます。
必要な場面で手助けしつつ、自立を尊重することが大切です。
声掛けや励ましはモチベーション維持につながります。
過剰な介助は運動機会を減らす恐れがあるため、必要な範囲に留めましょう。
地域のリハビリ・医療支援資源の活用
地域には、訪問リハビリや通所リハビリ、保健師による健康相談など、痙縮管理を支える資源があります。
これらを上手に組み合わせることで、在宅でも継続的なケアが可能です。
自治体の福祉サービスや患者会も有用な情報源となります。利用できる制度を把握しておくことで、経済的・精神的負担を軽減できます。
チームで考える“長期管理計画”の立て方
痙縮の長期管理には、医師、理学療法士、作業療法士、看護師など多職種の連携が不可欠です。
定期的な評価と目標の見直しを行い、状況に応じた対応を検討します。
この仕組みが整えば、症状の変化にも柔軟に対応でき、患者様やご家族様が安心して生活を続けられる環境を維持できます。
まとめ

この記事では、痙縮の定義や原因、日常生活への影響から、コントロールの重要性、リハビリでできること、自費リハビリの活用方法、そして長期的な管理のポイントまでを解説しました。
痙縮は放置すれば進行しやすい症状ですが、早期から適切な対応を行えば、生活の質(QOL)を維持・向上させることが可能です。
特に、「できることを維持し続ける」ことは、治すことと同じくらい価値があるという視点が重要です。
日々のセルフケアやご家族様のサポート、多職種連携による長期管理計画は、痙縮コントロールを継続する土台になります。
ご自身やご家族様が痙縮に悩まれている場合は、無理をせず、信頼できる医療・リハビリ専門職に相談してください。
適切な方法を知り、実行に移すことで、「また動ける」「生活がしやすくなった」という実感を得られる可能性があります。
もし本記事で解決できない疑問や不安があれば、ぜひ当施設までご相談ください。
患者様とご家族様が安心して前向きに生活できるよう、全力でサポートいたします。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

阿部 千恵
理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中)
1997年に理学療法士免許を取得。一般病院入職し、主に脳血管疾患患者様に対する急性期、回復期、外来のリハビリに携わる。脳神経疾患以外にも、神経難病、整形外科疾患、循環器疾患、呼吸器疾患に対するリハビリも経験。2015年に日本理学療法士協会認定理学療法士(脳卒中)を取得。これまでに学会発表や学会座長、研修会講師、論文執筆も行っている。2024年から脳神経リハビリセンター仙台に勤務。
私は、お客様の小さな変化を見逃さず、目標に向けて最善のリハビリを選択し、提供することを心掛けています。些細な変化であっても、積み重なることで大きな改善の礎となります。一歩ずつ着実に、お客様が目標を達成するための伴走者として、最大限のリハビリを行っていきたいと思います。





