お知らせ
NEWS
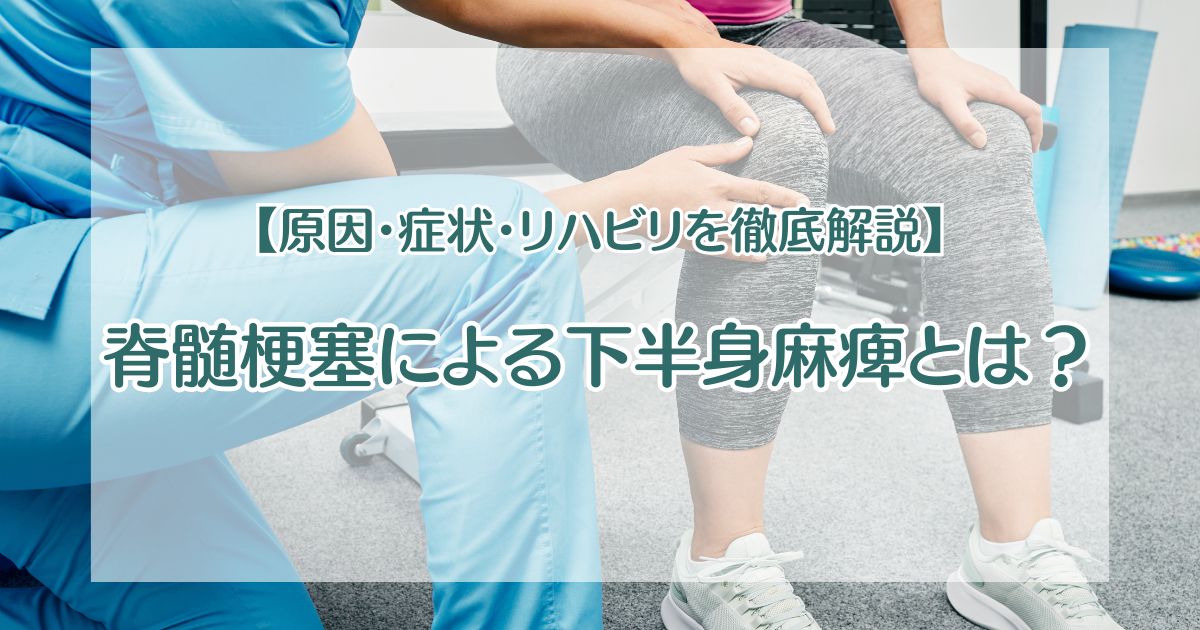

突然の脊髄梗塞で下半身麻痺に…「治るのか」「生活は続けられるのか」と不安を抱える患者様やご家族様は少なくありません。
放置すれば歩行や排泄の低下により日常生活に介助が必要になる場合があります。
本記事では原因や症状、リハビリと自費リハビリの可能性までお伝えします。
どんなリハビリをするのか、どのようなサポートが必要なのかをイメージしていただければ幸いです。
この記事でわかること

この章では「脊髄梗塞による下半身麻痺」について、症状の原因や生活への影響、回復の可能性、そしてリハビリや自費リハビリの選択肢までをお伝えします。
患者様やご家族様が知りたい疑問を、理学療法士の視点からわかりやすくお伝えします。
脊髄梗塞でなぜ下半身麻痺が起こるのか
脊髄梗塞とは、脊髄に血液を送る血管が詰まることで酸素や栄養が届かなくなる状態を指します。
脊髄は運動と感覚の両方を司るため、血流が途絶えると下半身の筋力低下や麻痺が生じます。
発症直後から強いしびれや力が入らない感覚が現れることが多く、早期の対応が予後を左右します。
主な症状と生活への影響
下半身麻痺に伴う症状は多岐にわたり、生活への負担も大きいです。
- 両足の麻痺や筋力低下により歩行が困難になる
- 腰から下の感覚が鈍くなり、しびれや感覚異常が続く
- 排尿や排便のコントロールが難しくなる膀胱直腸障害
これらの症状は日常生活の自立を妨げるため、ご家族様の介助負担も増える可能性があります。
治る可能性とリハビリの役割
下半身麻痺が完全に治るかどうかは、発症からの時間や損傷の範囲によって異なります。
統計では早期からのリハビリ介入により、約7割の患者様が歩行を再獲得できるとされています。
逆に、対応が遅れると関節拘縮や筋萎縮が進み、改善が難しくなるリスクがあります。
自費リハビリを含む改善の選択肢
医療保険や介護保険のリハビリには回数や期間の制限があります。
そのため改善が見込めても十分な訓練を継続できない場合があります。
その際は、自費リハビリ施設の利用が有効です。
- 90分以上の個別訓練による集中的な改善サポート
- 歩行支援ロボット(HAL)や電気刺激(FES)など先進的機器の活用
- ご家族様への介助方法や生活環境調整の具体的なアドバイス
このように、多角的なアプローチを組み合わせることで、患者様が再び歩行や日常生活に挑戦できる可能性が広がります。
脊髄梗塞と下半身麻痺の基礎知識

この章では、脊髄梗塞の仕組みや頻度、下半身麻痺の代表的な症状、そして脳梗塞との違いについてお伝えします。
基礎を理解することで、患者様やご家族様が病状を正しく把握し、リハビリや生活の工夫につなげることができます。
脊髄梗塞とは?発生の仕組みと頻度
脊髄梗塞とは、脊髄へ血液を送る血管が詰まり、酸素や栄養が届かなくなる病気です。
脊髄は身体の動きや感覚を伝える重要な役割を担っているため、障害が起こると下半身麻痺などの重大な症状が出ます。
発生頻度は脳梗塞に比べて非常に稀で、全体の脳血管障害の中でも数%程度に止まるとされています。
しかし、突然発症し重度の麻痺を残すことがあるため注意が必要です。
下半身麻痺の主な症状(運動障害・感覚障害・排尿排便障害)
脊髄梗塞による下半身麻痺では、以下のような症状が代表的です。
- 足の筋力低下や完全麻痺により歩行が困難になる
- 腰から下の感覚が鈍くなり、しびれや感覚異常が続く
- 尿意や便意がわかりにくくなる、または排泄がコントロールできない
これらの症状は患者様の日常生活を大きく制限し、ご家族様の介助が欠かせない状況につながります。
脊髄梗塞と脳梗塞の違い
脊髄梗塞と脳梗塞はどちらも血管が詰まることで起こる病気ですが、影響する部位が異なります。
脳梗塞は記憶や言語など高次脳機能にも障害を及ぼすのに対し、脊髄梗塞は主に運動と感覚の伝達経路に障害が起こります。
そのため、下半身麻痺や排尿排便障害といった身体機能への影響が中心となります。
脊髄梗塞は頻度が少ないため情報も限られますが、正しく理解し早期にリハビリへ取り組むことが回復の第一歩です。
下半身麻痺は治るのか?改善の可能性

この章では、脊髄梗塞による下半身麻痺がどの程度改善できるのか、回復の経過や予後、影響する要因、そして完全回復が難しい場合の生活支援についてお伝えします。
患者様やご家族様が現実的な見通しを持てるようお伝えします。
回復の経過と予後の目安
脊髄梗塞の下半身麻痺は、発症後の経過によって改善度が変わります。
早期からリハビリを始めた場合、およそ7割の患者様が歩行を再獲得できるという報告があります。
ただし回復には数か月から1年以上かかることも多く、忍耐強い取り組みが必要です。
一方で、重度の障害や高齢の方では回復が限定的となる場合があります。
その際も残存機能を維持し、生活の質を高めるリハビリは大きな意味を持ちます。
回復に影響する要因(発症からの時間・年齢・重症度)
下半身麻痺の改善度にはいくつかの要因が影響します。
- 発症から治療やリハビリを開始するまでの時間
- 年齢や基礎疾患の有無(高血圧・糖尿病など)
- 麻痺の程度(完全麻痺か不全麻痺か)
特に発症からの時間は重要で、早期介入が予後を大きく左右します。
完全回復が難しい場合の生活支援と工夫
完全回復が困難なケースでも、生活をより快適にする工夫は可能です。
リハビリを通じて残存機能を強化し、補助具を活用することで自立度を高められます。
- 車いすや歩行器の使用による移動手段の確保
- 段差解消や手すり設置など住環境の調整
- ご家族様が安全に介助できる方法の習得
このように、たとえ下半身麻痺が完全に治らなくても、リハビリと環境整備を組み合わせることで、患者様とご家族様の生活の質を守ることができます。
脊髄梗塞の原因と診断方法

この章では、脊髄梗塞がなぜ起こるのか、その主な原因やリスク因子、そして診断に用いられる検査方法についてお伝えします。
患者様やご家族様が発症の背景を理解することで、再発予防や早期発見にもつながります。
主な原因(動脈硬化・大動脈解離・手術後・外傷)
脊髄梗塞は、脊髄へ血液を送る血管が障害されることで発症します。
具体的には以下の要因が多く報告されています。
- 動脈硬化:血管が狭くなり血流が不足する
- 大動脈解離:大動脈の壁が裂け血流が遮断される
- 心臓や大血管の手術後:血流変化や血栓形成が原因になる
- 外傷:事故や強い衝撃による血管損傷
いずれも血流が途絶えることで脊髄に酸素が届かなくなり、麻痺や感覚障害が生じます。
リスク因子(高血圧・糖尿病・喫煙など)
脊髄梗塞の発症リスクを高める背景には生活習慣病が関与しています。
- 高血圧:血管に負担をかけ続ける
- 糖尿病:血管がもろくなり血栓ができやすくなる
- 脂質異常症:コレステロールが血管を詰まらせる
- 喫煙:血管を収縮させ血流を悪化させる
これらの因子を管理することは、脊髄梗塞の予防だけでなく再発防止にも直結します。
診断に用いられる検査(MRI・CT・神経学的評価)
脊髄梗塞は発症直後に正確に診断することが難しい病気です。
そのため複数の検査を組み合わせて判断します。
- MRI(磁気共鳴画像法):脊髄の血流障害や損傷部位を詳細に確認できる
- CTスキャン:急性期の出血や脊椎の異常を把握できる
- 神経学的評価:下肢の運動や感覚の状態を丁寧に検査する
特にMRIは診断の中心となり、発症から早期に行うことで治療方針の決定に役立ちます。
リハビリと日常生活へのサポート

この章では、脊髄梗塞による下半身麻痺に対して行われるリハビリの流れと、患者様やご家族様が日常生活で取り組める工夫についてお伝えします。
急性期・回復期・自費リハビリといった段階ごとの特徴を知ることで、改善へ取り組むことができます。
急性期のリハビリ(関節可動域・筋力維持)
発症直後は安静が中心になりますが、関節の動きを保ち筋力を維持するリハビリが早期から重要です。
関節可動域訓練や体位変換を行うことで、関節拘縮や褥瘡を予防します。
※褥瘡(じょくそう):床ずれ
理学療法士や作業療法士が患者様の無理のない範囲で介入し、身体機能の維持・向上に努めていきます。
回復期のリハビリ(歩行訓練・感覚トレーニング)
症状が安定すると、歩行や感覚の改善を目指すリハビリが中心となります。
歩行器や杖を用いた歩行練習、段階的な筋力強化、感覚刺激によるリハビリが行われます。
継続することで少しずつ自立度が高まります。
この時期のリハビリは、その後の生活の自立を目指す上でとても大切です。
自費リハビリ施設の活用
公的保険制度ではリハビリの期間や頻度に制限があります。
そのため、保険外の自費リハビリ施設を併用する方が増えています。
自費施設では、以下のような特長があります。
- 90分など長時間のリハビリを継続できる
- ロボットリハビリなどの先端機器によるトレーニングが受けられる
- ご本人の生活目標に合わせた個別プログラムが提供される
費用面の検討は必要ですが、選択肢の一つとして知っておく価値があります。
脳神経リハビリセンターをご利用いただいた患者様とご家族様の声をご紹介します。
自費リハビリでは、生活に直結した「できること」が増える実感が得られやすくなります。
それぞれの目標に沿ったリハビリによって、達成感が得られるのも特長です。
当施設でも、次のような喜びの声が届いています。
- 「自分で靴を履けるようになり外出が楽しくなった」
- 「階段の昇り降りができ、介助なしで外出できた」
↓↓↓実際のお客様のリアルな声はこちらでご確認いただけます。
ご家族様が支える上でのポイント(介助・心理的支援・生活環境調整)
患者様の回復には、ご家族様の支えも欠かせません。
介助の工夫や心理的な支援、生活環境の整備が日常の安定につながります。
- 立ち上がりや移乗の介助方法を専門職から学ぶ
- 励ましすぎず見守る姿勢を意識する
- 段差解消や手すり設置など住環境を整える
こうした工夫を取り入れることで、患者様が安心して生活を続けられる環境を作ることができます。
まとめ|下半身麻痺と向き合うために

この章では、脊髄梗塞による下半身麻痺と向き合う際に大切な考え方をお伝えします。
早期診断とリハビリの重要性、生活の工夫そして患者様とご家族様が取り組める支援をお伝えします。
早期の診断・リハビリ開始が回復の鍵
脊髄梗塞は発症直後の対応が予後を左右します。
MRIなどによる正確な診断と早期のリハビリ開始が、歩行再獲得や機能改善につながります。
発症から時間が経過するほど改善の可能性は低くなるため、迅速な対応が重要です。
治る可能性と生活の工夫を両立させることが大切
完全な回復が難しい場合でも、残存機能を引き出すリハビリや補助具の活用で自立度を高めることができます。
さらに住環境を整えることで、安全で快適な生活が実現します。
「治すこと」と「工夫して生活を続けること」を両立させることが大切です。
患者様・ご家族様が希望を持って取り組める支援の在り方
患者様とご家族様が安心して前に進むためには、医療やリハビリの専門職だけでなく、心理的な支えや生活支援も不可欠です。
励まし合いながら取り組むことで、困難を乗り越える力になります。
下半身麻痺は決して諦めるべき症状ではありません。
適切なリハビリとサポートを継続することで、生活の質を高め、再び希望ある未来を描くことができます。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

髙橋 克弥
理学療法士
2015年に理学療法士免許を取得。一般病院に勤務。
回復期病棟、一般・療養病棟、地域包括ケア病棟、外来リハビリといった様々なステージでのリハビリ業務を経験。学会参加や学会発表も経験。脳血管疾患、運動器疾患など多くの患者様やその御家族に携わる。
2022年からクリニックに勤務。
国際マッケンジー法認定セラピスト取得。再生医療立ち上げメンバーとして携わる。
2024年から脳神経リハビリセンター仙台に勤務。
私は「お客様が主役」をモットーに皆様の希望に添えるリハビリを提供します。
自分の限界が利用者様の限界になるため、自分の限界を決めずに諦めず、試行錯誤しながら一人一人にあったリハビリプログラムを考えています。
脳神経リハビリセンター仙台に興味を持っていただいたお客様には後遺症をあきらめないで欲しいです。リハビリの可能性を知ってほしいと思います。当社のような自費リハビリ施設は、まだ東北地方ではほとんど知られていません。初回の無料体験プログラムを利用いただき、自分がどこまでよくなるか、可能性を感じてほしいと思います。
目標達成に向かって、共に進んで行きましょう。





