お知らせ
NEWS
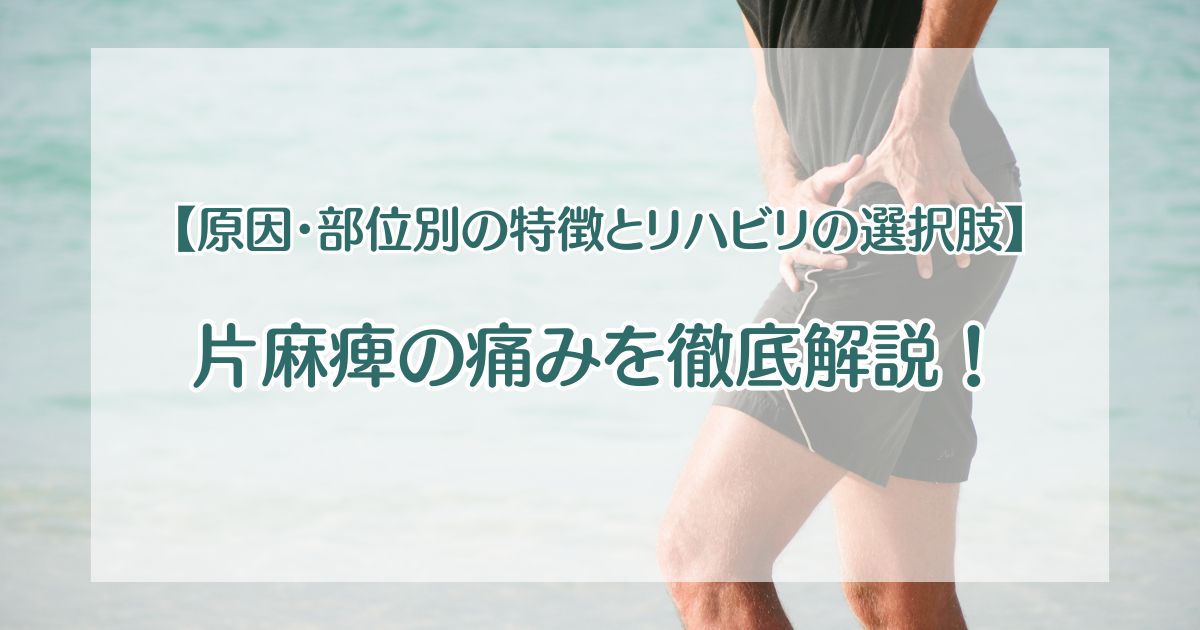

片麻痺に伴う肩や股関節の痛みで生活が辛いと感じていませんか?
患者様もご家族様も不安は尽きません。
放置すればリハビリ中断や生活の質低下を招く恐れがあります。
本記事では原因と緩和方法、セルフケア、自費リハの選択肢まで解説します。
是非ご一読ください。
片麻痺と痛みの関係性を理解する

片麻痺に伴う痛みは、日常生活の質やリハビリの継続に大きく影響します。
この章では、痛みの基本的な背景や「なぜ痛むのか」という疑問、そして患者様やご家族様が抱えやすい不安について解説します。
片麻痺に伴う痛みとは?(発症の背景と特徴)
片麻痺の痛みは、脳卒中などの脳血管障害の後遺症として多くみられます。
脳の損傷により筋肉や関節をコントロールしにくくなり、動きの不均衡や姿勢の崩れが生じます。
その結果、肩関節の不安定さや手足のこわばりが痛みとして現れます。
「なぜ痛むのか?」よくある疑問と基本的な考え方
片麻痺で痛みが生じる理由は一つではありません。
代表的な原因は以下の通りです。
- 亜脱臼:主に肩関節に見られます
- 痙縮:筋肉が異常に緊張して固くなる状態で、動作時の痛みにつながります
- 中枢性疼痛:脳が感覚を誤って「痛み」と認識してしまう症状
- 不動による痛み:同じ姿勢が続くことによる筋肉・関節への負担となり、痛みにつながります
これらは複数が重なって起こることも多く、正確な評価が重要です。
原因を特定しないまま我慢すると、リハビリの進行を妨げる可能性があります。
患者様・ご家族様が感じやすい不安と課題
片麻痺の痛みは、患者様ご本人だけでなくご家族様にも負担を与えます。
「この痛みは治るのか」「動かしてよいのか」といった不安を抱えやすいのです。
一方で、正しい知識を持ち、専門職と連携すれば改善や予防は十分に可能です。
理学療法士や作業療法士が関わることで、安心してリハビリを継続できる環境を整えられます。
その結果、痛みを軽減しながら日常生活の幅を広げることが期待できます。
片麻痺で起こりやすい痛みの原因

片麻痺に伴う痛みの原因は一つではなく、複数が重なり合って現れることが多いです。
この章では、代表的な原因を具体的に解説し、痛みを理解するための基礎を整理します。
肩関節の亜脱臼や筋肉のアンバランスによる痛み
片麻痺では、肩周囲の筋力が弱くなります。腕の重みを肩周囲の筋肉で支えられなくなり
その結果、肩関節が外れかける「亜脱臼」が起こりやすく、強い痛みの原因となります。
適切なポジショニングと肩関節周囲を支える筋肉を鍛える運動が予防と改善に有効です。
痙縮・拘縮による動作時の痛み
痙縮とは、麻痺後に筋肉が過剰に緊張して動かしにくくなる症状です。
さらに長期間動かさないと関節が固まる拘縮が進行し、動作時に鋭い痛みが出ます。
中枢性疼痛(脳の感覚異常による痛み)
中枢性疼痛とは、脳が感覚情報の刺激を「痛み」と誤認識する状態です。
服が擦れるだけで痛む、冷たさを痛みとして感じるといった症状が特徴です。
完全に消すことは難しいですが、リハビリや薬物治療で軽減を目指せます。
姿勢不良や長時間同じ姿勢による痛み
麻痺側をかばう姿勢や、長時間の同一姿勢は筋肉や関節に負担をかけます。
特に座位や臥位での姿勢不良は肩や腰に影響し、慢性的な痛みを招きます。
座位保持具やクッションを活用したポジショニングが効果的です。
合併症(肩手症候群、関節炎など)に関連する痛み
脳卒中後は「肩手症候群」と呼ばれる合併症が起きやすく、肩から手にかけて腫れや強い痛みを伴います。
また、関節炎や神経痛が重なると、痛みはさらに複雑になります。
- 肩手症候群:強い痛み・腫れ・こわばりを伴う
- 変形性関節症:関節に負担がかかり炎症が起きる
- 末梢神経障害:痺れや灼熱感が加わることもある
複数の要因が関与する場合も多いため、理学療法士・作業療法士による評価と医師の診察を組み合わせることが重要です。
正しい理解ができれば、必要なサービスやセルフケアを選びやすくなり、安心して生活を続けられます。
部位別にみる片麻痺の痛みと対応

片麻痺の痛みは身体のさまざまな部位に現れます。
この章では、肩・股関節や膝・手首・非麻痺側の痛みをそれぞれ解説し、対応の工夫を紹介します。
部位ごとの特徴を理解することで、適切なリハビリやセルフケアにつなげることができます。
肩の痛み(肩関節周囲の動作・上腕部の痛みを含む)
片麻痺の痛みで最も多いのは肩の痛みです。
亜脱臼や肩関節周囲筋の筋緊張に障害があり、腕をあげる・横に開く動作などで痛みにつながります。
予防には正しいポジショニングと肩甲骨周囲の運動が不可欠です。
股関節・膝の痛みと歩行時の負担
歩行の際に股関節や膝へ強い負担がかかり、痛みを訴える患者様も多くいます。
特に麻痺側をかばって歩くことで関節に余分なストレスが加わります。
手関節・手首の痛みと日常生活動作への影響
片麻痺では、手関節や手首の痛みが食事や更衣など日常動作を妨げます。
持続的な筋緊張や関節の誤使用が原因となりやすいです。
放置すると関節の変形や拘縮につながる恐れがあります。
早期からのストレッチや装具使用で予防を図ることが大切です。
非麻痺側に生じる痛み(二次的なオーバーユースの問題)
片麻痺では非麻痺側を使う割合が増え、過剰使用による痛みが起こることもあります。
肩・腰・膝など、麻痺側をかばうための非麻痺側の負担は大きく、日常生活や介助動作に影響します。
- 杖や歩行器を長期間使用した際の肩の痛み
- 階段昇降時の膝痛や腰痛
- 介助や作業で手首を痛めるケース
非麻痺側の痛みは軽視されがちですが、リハビリの妨げとなるため早期から注意が必要です。
負担を分散させる運動や補助具の活用により、長期的な生活の質を守ることができます。
片麻痺の痛みを和らげるリハビリとセルフケア

片麻痺の痛みは放置すると悪化し、日常生活やリハビリの継続を妨げます。
この章では、理学療法士・作業療法士が行うリハビリの役割や、ご自宅で実践できるセルフケアを紹介します。
正しい方法を取り入れることで、痛みを軽減し生活の幅を広げることが可能です。
理学療法士・作業療法士によるリハビリの役割
痛みの原因を評価し、関節や筋肉に合わせた運動を行うのが専門職の役割です。
正しい動作指導や日常生活での姿勢指導により、再発防止につながります。
リハビリは単なる運動ではなく、痛みを抑えながら機能回復を目指す治療のです。
関節可動域訓練・筋緊張コントロールの工夫
関節を柔らかく保つ可動域訓練は、痛み予防の基本です。
痙縮で筋肉が硬くなっている場合は、ストレッチや低負荷の運動で緊張を和らげます。
正しい姿勢とポジショニングの重要性
姿勢の崩れは痛みの大きな要因です。
座位や臥位での正しい姿勢保持は、肩や股関節への負担を軽減します。
クッションや支えを利用することで、無理のない姿勢を維持しやすくなります。
自宅でできるセルフケア(温熱・ストレッチ・ポジショニング)
ご自宅でできる工夫も効果的です。
- 温熱療法:蒸しタオルや温パックで血流を促進
- ストレッチ:毎日の軽い運動で筋肉の柔軟性を保つ
- ポジショニング:寝る姿勢や座る姿勢を工夫し関節を守る
セルフケアは無理なく続けられる範囲で行い、痛みが増す場合は中止して相談してください。
薬物療法との併用(医師と連携した安全な対応)
片麻痺の痛みには薬物療法が有効な場合もあります。
鎮痛薬や痙縮改善薬は医師の判断で処方され、リハビリとの併用で効果を高められます。
自己判断で薬を増減すると副作用のリスクがあるため必ず医師に相談してください。
自宅での工夫や薬物療法だけでは十分でない場合もあります。
そのようなときは、医療保険や介護保険の枠を超えて継続できる自費リハビリが選択肢になります。
十分な時間を確保した専門的なアプローチにより、痛みの軽減と機能改善を両立できる可能性があります。
リハビリとセルフケアを組み合わせることで、痛みの緩和と機能回復を同時に目指すことができます。
患者様・ご家族様が前向きに取り組むことで、生活の質を高める道が広がります。
自費リハビリで得られる継続的なサポートの価値
医療保険や介護保険のリハビリには期間や回数の制限があります。
十分な訓練を受けられず、改善の可能性を残したまま終了する方も少なくありません。
そのまま放置すると再び機能低下を招くリスクがあります。
代替策として注目されるのが自費リハビリです。
時間や内容を柔軟に設定でき、専門職のマンツーマン支援を継続的に受けられます。
↓↓↓自費リハビリの選び方については、こちらの記事をご参照ください。
【料金・頻度・施設選定まで解説!】失敗しない自費リハビリの選び方
リハビリは単なる回復の手段ではなく、患者様とご家族様が安心して生活を続けるための伴走者となります。適切な支援を受けることで、諦めずに社会参加を目指すことができます。
脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。
【発症後1年11ヶ月】 60代男性・K.T様・脳出血・左片麻痺の改善事例
体幹や左肩関節周囲の筋肉は低緊張で肩関節には軽度の亜脱臼もありました。
左上肢を挙上しようとしても肩が動かず肘が曲がり、手指も強く握りこんでしまう状態でした。
当初は肩関節周囲の安定性を高める介入や、HALを使用し手首の上げ下げや前腕を捻る動きを促しました。
現在では代償動作は残存していますが、肩が上がるようになり手指や肘も身体の前方で保持できるようになり亜脱臼もほぼ無くなりました。
また、肩を前後に動かす、肘を前に伸ばすこともできるようになってきています。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【発症後1年11ヶ月】 60代男性・K.T様・脳出血・左片麻痺の改善事例
まとめ|痛みと向き合いながら生活の幅を広げるために

脳卒中に伴う痛みは複雑で、患者様やご家族様にとって大きな課題です。
この章では、痛みを放置せず早めに対応する重要性、リハビリを継続するための工夫、さらに自費リハビリの可能性についてまとめます。
痛みを放置せず、早めの評価と対応が大切
痛みをそのままにすると関節が固まり、動作の制限や生活の質低下につながります。
早期の評価とリハビリ介入が、改善への第一歩です。
症状が出た時点で医師やセラピストに相談することが望まれます。
リハビリを継続するための工夫とご家族様の支え
痛みが強いとリハビリを諦めてしまう方もいます。
しかし、休止は回復を遅らせる要因になります。
一緒に取り組む姿勢が、患者様の意欲を高めます。
保険リハ終了後に選べる自費リハビリの可能性
医療保険や介護保険でのリハビリは期限があり、必要な支援が十分に受けられないことがあります。
その際の選択肢が自費リハビリです。
時間を十分に確保し、個別性の高いプログラムで痛みの緩和と機能改善を継続できます。
経済的負担は増えますが、継続的な回復を求める方に有効です。
生活の質を高めるためにできる前向きな選択肢
痛みと向き合うことは大きな挑戦ですが、適切なリハビリ・セルフケア・医療との連携で改善は可能です。
- 専門職による正確な評価とリハビリ
- 自宅で続けられるセルフケアの実践
- ご家族様による日常的なサポート
- 自費リハビリなど多様な選択肢の活用
これらを組み合わせることで、痛みに左右されず生活の幅を広げる未来につながります。
患者様・ご家族様が安心して前を向けるよう、希望を持った支援を続けていくことが重要です。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

石橋 渉
理学療法士
2021年に理学療法士免許を取得。同年から名古屋市内の大学病院、2023年より三重県内の大学病院で勤務。急性期・回復期・維持期の様々な分野でのリハビリを経験。主に脳血管疾患・整形外科疾患の方のリハビリに携わる。
2025年8月より脳神経リハビリセンター名古屋に勤務
私は、「お客様に寄り添ったリハビリを提供する」を心がけております。
お客様のライフゴールに少しでも近づいて行けるよう、安心して通えるように、持ち前の包容力を生かして精一杯のサポート致します。
目標に向かって一緒に頑張りましょう!





