お知らせ
NEWS
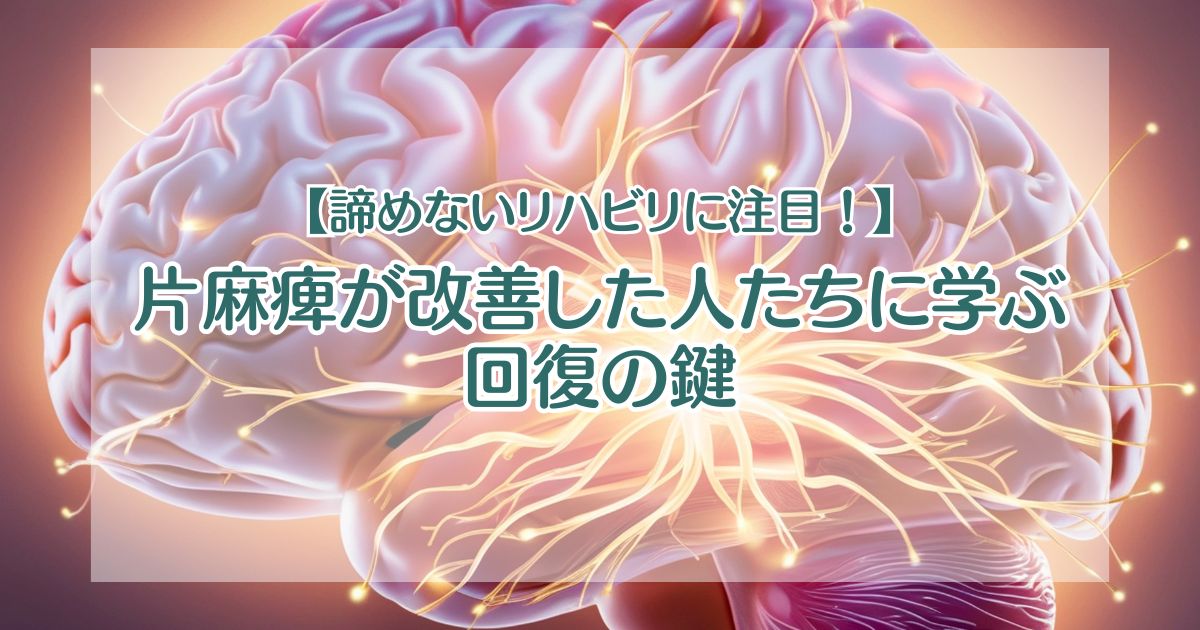

片麻痺の改善を諦めかけていませんか?
「もう動かない」と言われても、実際に回復を続ける方は多くいます。
適切なリハビリを行わなければ、筋力低下や関節の動きの制限が進行し、生活の幅が狭まる可能性があります。
本記事では、当センターで実際に改善された方々の事例と、その共通点を理学療法士が解説します。
「もう遅い」と思う方にも希望と再起のヒントが見つかります。
片麻痺は改善するのか?|回復の仕組みと時間の限界

この章では、片麻痺がどのようにして起こり、どのような仕組みで回復していくのかを解説します。
また、「6か月の壁」と呼ばれる時期の意味と、改善を続けるための考え方についてもご紹介します。
回復のメカニズムを知ることで、リハビリを継続するモチベーションを高めることができます。
片麻痺とは何か:脳梗塞・脳出血による神経損傷の仕組み
片麻痺とは、脳の損傷により、体の片側に力が入りにくくなる症状のことです。
脳の運動をつかさどる領域が障害されると、反対側の手足に麻痺が生じます。
たとえば、右脳が損傷すれば左半身、左脳が損傷すれば右半身に麻痺が起こります。
脳卒中の多くは「脳梗塞」と「脳出血」に分類されます。
脳梗塞は血管の詰まりによる血流不足、脳出血は血管の破裂による出血が原因です。
どちらも脳細胞への酸素や栄養の供給が絶たれることで神経が損傷します。
回復を目指すには、残された神経をいかに有効に働かせるかが重要です。
損傷した部分の代わりに、健康な脳の領域が動きを再び学習していくことが、リハビリの基本となります。
回復のプロセス:神経可塑性とリハビリの関係
- 神経可塑性の促進
脳の可塑性とは、経験や学習によって脳が変化し、適応する能力のことです。
リハビリテーションは、脳の神経可塑性、つまり損傷後の脳が新たな神経経路を形成することなどを利用して、機能の再建を促進していく事を目指しています。
積極的なリハビリテーションは、損傷した脳領域の周辺での新たな神経経路の形成を助け、失われた機能の一部を回復させる可能性があります。
しかし、リハビリテーションに一貫性がなければ、その新しい神経接続は十分な繋がりを持てません。
リハビリテーションは、「反復性」と「一貫性」が大切です。
たとえば、手がうまく動かない場合でも、
- 触覚刺激や筋肉の収縮を促す訓練
- ロボットリハや装具による反復運動
- 姿勢や目線を変えて動作を引き出す工夫
こういった事などで神経の再教育を助けます。
重要なのは、諦めずに続けることが回復の鍵であるという点です。
一時的に停滞しても、刺激を変えることで脳の学習が再び進む可能性があります。
「6か月の壁」とは?|改善が続く人の共通点
一般的に「脳卒中後6か月を過ぎると回復が止まる」と言われてきました。
これは、急性期の自然回復が落ち着く時期を示すものであり、「それ以上良くならない」という意味ではありません。
近年の研究では、発症から1年以上経過しても機能が改善する例が多く報告されています。
特に、自費リハビリなどで継続的に刺激を与えることで、動作の精度や筋力が向上する方も少なくありません。
- リハビリを定期的に続けている
- 「できたこと」を記録し、前向きな意識を保っている
- 生活動作の中で自然に練習を取り入れている
このような方は、発症から時間が経っても回復を続ける傾向があります。
改善を止めるのは時間ではなく、刺激の有無であることを理解し、環境や方法を見直すことが大切です。
片麻痺が改善した人の実例

この章では、当センターで実際に片麻痺が改善した方々の事例を紹介します。
発症からの期間や症状はそれぞれ異なりますが、共通しているのは「諦めずにリハビリを続けたこと」です。
ここでは、リハビリ内容と成果を具体的にお伝えし、回復へのヒントをお届けします。
【発症後2年8ヶ月】40代・男性・右脳梗塞・左片麻痺の歩行の改善事例
ご自宅退院後は就労支援事業所に約11ヶ月間通われ、週5日勤務で職場復帰を果たされました。
装具なしでの歩行が可能となったものの、「旅行に行きたい」「将来的にはもう一度走りたい」という想いから、知人の紹介で当センターの無料リハビリ体験にお越しいただきました。
現在はお仕事を続けながら、休日に週1回のペースで継続的にリハビリを行われています。
体験時は、屋内外で装具なしの歩行が可能でしたが、屋外では慣れた道以外ではT字杖とご家族の見守りが必要な状態でした。
また、歩行スピードが遅く、横断歩道を渡り切れないことや、歩行後の疲労感を強く感じておられました。
リハビリを重ねる中で、左足の支持力や体幹の安定性が向上し、歩行中に見られていた骨盤の引き上げなどの代償動作が軽減。
それに伴い、歩行スピード・安定性ともに改善が見られました。
現在では、当施設まで公共交通機関を利用してお一人で通所されるようになり、栄の5車線あるスクランブル交差点も一度で渡り切れるようになっています。
今後は先ず「旅行に行く」という目標に向け、さらに歩行スピードと持久力の向上を目指してリハビリを継続されています。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【発症後2年8ヶ月】40代・男性・右脳梗塞・左片麻痺の歩行の改善事例
【発症後1年11ヶ月】40代男性・橋出血・複視/バランス障害の改善事例
40代男性は、橋出血により平衡感覚が著しく低下し、複視(物が二重に見える)も併発していました。
当センターでは、体幹の安定性を高めるための座位バランス訓練と、視覚刺激を利用した注視トレーニングを導入。
初期はわずか数秒しか立位保持ができませんでしたが、3ヶ月後には安定した立位姿勢を維持できるようになりました。
また、趣味の釣りに再び挑戦できるようになり、外出の機会が増えたことで社会参加への意欲も回復。
【発症後11ヶ月】60代男性・脳出血・右片麻痺の上肢機能改善事例
60代男性は右上肢の麻痺により、家事や細かい作業が困難な状態でした。
当センターでは、装具を用いたリーチ動作訓練とタオル運動による巧緻動作の再教育を実施。
日常生活動作(ADL)の中で「自分で行えること」を増やす方針で、動作練習を丁寧に積み重ねました。
その結果、茶碗洗いや洗濯干しなど、家事動作の自立が進み、笑顔で「家の中でも役割が増えた」と語られています。
上肢リハビリは地道ですが、小さな成功体験の積み重ねが大きな変化を生みます。
【発症後2年7ヶ月】60代男性・右片麻痺の長期改善事例
この方は発症から2年以上経過しており、一般的なリハビリ期間を超えていました。
しかし、自費リハビリを継続する中で、歩容と手指の協調性が徐々に改善。
特に指の伸展訓練では、指先にわずかな動きを感じた瞬間から積極的に家庭練習を取り入れました。
現在では、屋外歩行も安定し、字を書く練習にも挑戦されています。
発症から長期間経過していても、正しい方向に努力を続けることで機能は再び変化します。
「遅くても諦めない姿勢」が、神経の再学習を促す最大の原動力です。
共通点に見る“改善する人”の特徴
当センターで回復を遂げた方々には、いくつかの共通点があります。
- 定期的な通所を継続されている
- 生活の中にリハビリの要素を取り入れている
- ご家族様が小さな変化を見逃さず励ましている
これらの姿勢が、発症後の長期回復を支える土台となっています。
改善は特別な才能ではなく、「継続と工夫」で誰にでも起こりうることです。
片麻痺改善のためのリハビリ|専門家が推奨する3つの柱

この章では、片麻痺の改善を目指すうえで理学療法士が重視する3つのリハビリの柱について解説します。
発症時期や症状の程度にかかわらず、共通して必要なのは「継続」「根拠」「環境」の3要素です。
ここで紹介する内容は、医療保険外リハビリでも実践できる再現性の高い方法です。
① 早期・継続的なリハビリの重要性
脳卒中後の回復には、早期開始と継続性が欠かせません。
脳が損傷を受けた直後は神経細胞が再びつながりやすい状態にあり、この時期にリハビリを始めると改善効果が高まります。
一方で、早期にリハビリを始められなかった場合でも遅すぎることはありません。
脳には「可塑性(かそせい)」という再学習の力があり、適切な刺激を続ければ時間が経過しても変化は起こります。
- 入院期に得た動きを生活期でも維持する
- 退院後も定期的にリハビリを継続する
- 家庭内でも「動かす習慣」を意識する
この3点を意識するだけでも、廃用症候群(使わないことでの機能低下)を防ぎ、回復の土台を維持できます。
「やめないこと」が最大のリハビリです。
↓↓↓脳梗塞後のリハビリ開始時期の重要性について、是非こちらの記事をご覧ください。
脳梗塞後のリハビリはいつから?【リハビリセンターの効果も解説!】
② 科学的根拠に基づくトレーニング|脳科学に基づいたリハビリアプローチ
片麻痺の改善には、脳科学に基づいたアプローチが欠かせません。
近年の研究では、脳が「動き」だけでなく「意図」や「感覚入力」を通して再び学習することが明らかになっています。
そのため、リハビリは単に筋肉を鍛えるだけでなく、「脳が動きを理解し直す過程」を重視して行うことが重要です。
当センターでは、ロボットリハビリ(HALなど)や、ニューロリハビリテーションの考え方を取り入れた訓練を行っています。
ロボットリハでは、筋肉のわずかな電気信号を検出し、本人の「動かしたい」という意思に合わせて動作を補助します。
これは脳が「自分で動いた」という感覚を再び学習することにつながり、神経の再教育(再マッピング)を促進します。
また、認知神経的な視点では、患者様が「どのように感じ、どう動かそうとしているか」を重視します。
たとえば、同じ動作を繰り返す際も、「どこに力を入れるか」「動きの変化をどう感じるか」を意識してもらうことで、脳が動きをより正確に再構築できます。
- 動作中の感覚や重心位置を意識する
- 目標とする動きをイメージしながら実施する
- セラピストが姿勢や視線を調整して脳への刺激を最適化する
このように、脳科学的な根拠に基づいたトレーニングは、単なる筋トレではなく、「脳の学び直し」を促すアプローチです。
③ 在宅・自費リハの活用|保険外でも「改善」を追求できる選択肢
発症から半年を過ぎると、医療保険でのリハビリは制限される場合があります。
その結果、「これ以上は回復しない」と誤解されることも少なくありません。
しかし、自費リハビリ(保険外リハビリ)では、期間や回数に制限がなく、必要な分だけ集中的に訓練を継続できます。
実際に当センターでも、発症から2年以上経過してから歩行・手指の改善を得た方が複数おられます。
その共通点は「新しい刺激を取り入れた継続」です。
- 週1回でも長期的に通い続けている
- 家庭練習をセラピストと一緒に設計している
- 環境を変えてモチベーションを維持している
このように、「環境を変えること」も脳への刺激となり、再び回復を呼び起こす要因となります。
自費リハは費用面の負担もありますが、短期間で成果を出すことを目的に設計されており、効率的な回復を望む方に適しています。
「もう遅い」と思う時こそ、行動を変えるチャンスです。
片麻痺の改善を妨げる落とし穴|やってはいけないこと

この章では、片麻痺の回復を目指す上で注意すべき3つの落とし穴を解説します。
「頑張っているのに良くならない」と感じる背景には、知らず知らずのうちに回復を妨げる習慣がある場合があります。
理学療法士の視点から、避けるべき行動とその代替策をわかりやすく紹介します。
「動かないから休ませる」は誤り|廃用症候群のリスク
「無理をさせないように」と体を休ませすぎると、廃用症候群(はいようしょうこうぐん)を引き起こす可能性があります。
廃用症候群とは、動かさないことで筋力や関節可動域が低下し、心肺機能まで弱まる状態のことです。
特に脳卒中後の片麻痺では、麻痺側を使わない時間が長くなるほど、回復スピードが遅くなります。
- 日常生活で「できる動き」を意識的に使う
- 安全な範囲で軽い運動を続ける
- 痛みや疲労が強い場合はセラピストに相談する
休むことが必要な場面もありますが、完全に動かさないことが回復の妨げになる点を理解しておきましょう。
過剰な自己流リハビリの危険性
インターネットやSNSには、リハビリ情報が数多く存在します。
しかし、自己判断で強度の高い運動を続けると、筋肉や関節に負担をかけ、痛みや炎症を起こすリスクがあります。
また、動作が誤ったまま反復されると、脳がその誤った動きを「正しい動作」として覚えてしまうこともあります。
自己流ではなく、専門家の評価と助言を受けながら行うことが大切です。
例えるなら、100回の間違った練習より、1回の正しい動作が脳を変えます。
モチベーションの低下を防ぐ「小さな成功体験」の積み方
リハビリは長期戦であり、結果がすぐに出ない期間が続くと意欲を失いやすくなります。
そのような時こそ、「昨日よりできたこと」を意識的に見つけることが重要です。
具体的には、次のような工夫が効果的です。
- 動作練習を動画で撮影し、前回との違いを確認する
- 1日の中で「できた動き」を記録する
- ご家族様が変化を声に出して伝える
こうした積み重ねが自信となり、継続意欲を高めます。
また、ご家族様の「頑張ってるね」「前より動いたね」というポジティブな言葉は、リハビリの最大の支えになります。
リハビリは孤独な戦いではなく、支え合いながら続ける取り組みです。
まとめ|改善は“奇跡”ではなく“積み重ね”から生まれる

これまでの内容では、片麻痺の改善に必要な仕組み、実際の回復事例、そして避けるべき落とし穴について解説しました。
結論としてお伝えしたいのは、片麻痺の回復は特別な奇跡ではなく、日々の小さな積み重ねによって生まれるということです。
脳には「神経可塑性」という再学習の力があり、時間が経っても正しい刺激を与え続ければ変化を起こせます。
発症から半年を過ぎても、1年を超えても、適切なリハビリを継続することで動作や感覚が再び戻る可能性があります。
重要なのは、「もう遅い」と思わずに新しい一歩を踏み出すことです。
- 小さな変化を喜びながら続ける
- 必要なサポートを専門家に相談する
- 自分のペースで焦らず取り組む
当センターの患者様の多くも、「最初は1歩がやっとだった」方が、日々の努力によって確かな変化を感じ取られています。
ご家族様の支えや励ましも、回復を支える大切な力です。
改善は努力の結果であり、誰にでも訪れる可能性があります。
私たちは「もう一度動きたい」という想いに寄り添い、最適なリハビリをご提案します。
このページを閉じたあとも、今日からできることを一つずつ始めてみてください。
その一歩が、未来の大きな回復につながります。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

市橋 賢
理学療法士
2017年に理学療法士免許を取得。回復期病棟、外来リハビリ、訪問リハビリを幅広く経験。2022年にチームリーダーとして名古屋市内の回復期病棟立ち上げ。
2025年4月から脳神経リハビリセンター名古屋栄に勤務。
私が、理学療法士を目指したのは、自分自身がリハビリを受けた経験があったからです。
そのときに味わった「また動けるようになった!」という感動は、一生忘れません。
一方で、祖母はリハビリを途中で諦めてしまい、寝たきりの生活になってしまいました。
その話を聞いたときの悔しさと無力感は、今でも忘れられません。
だからこそ私は、「当たり前にできたことを、もう一度当たり前にできるように」、一人ひとりに徹底的に寄り添いながらサポートしていきます。
リハビリは大変ですが、どこか安らぎを感じながら、共に努力していける関係性を大切にして、前向きな一歩を一緒に積み重ねていけたらと思います。





