【発症後1年】50代・男性・脳出血(後藤様)・左片麻痺の歩行の改善事例
- 50代
- 男性
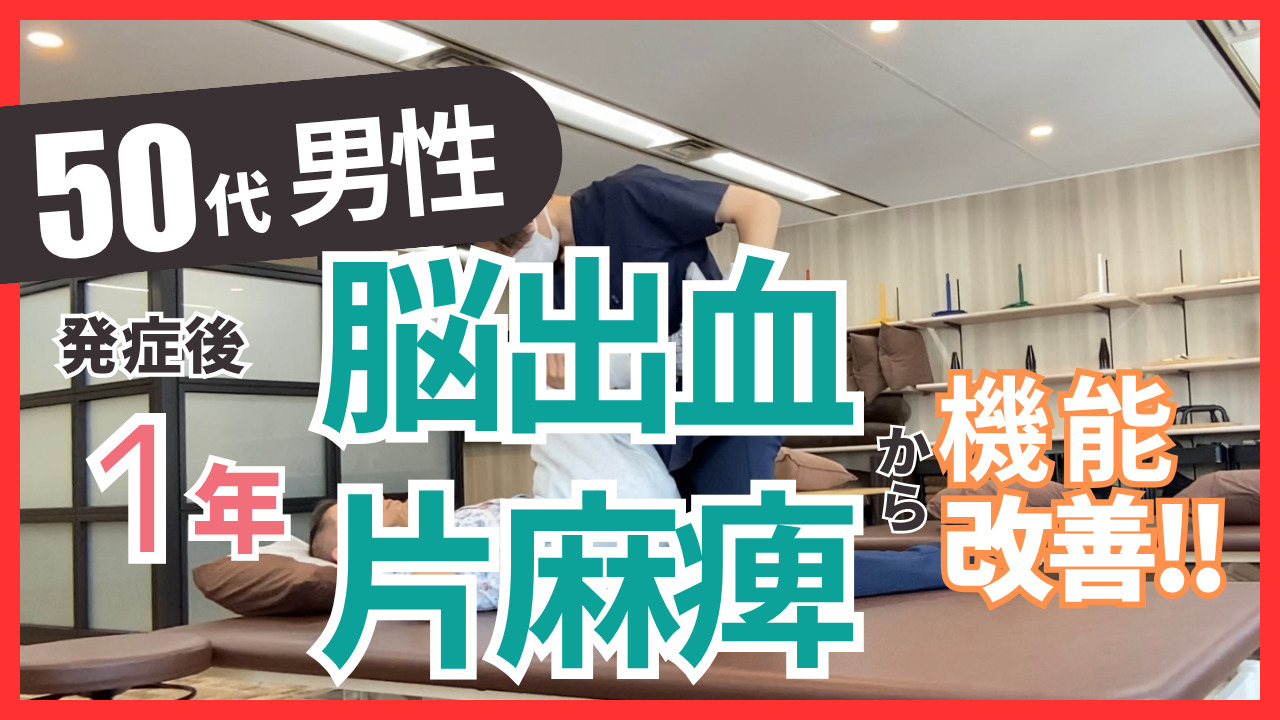
ご利用者様情報
- 年代
- 50代
- 性別
- 男性
- 疾患名
- 脳出血
- 発症からの期間
- 約1年
- 症状
- 左片麻痺
- ご利用期間・回数
- 3ヶ月・週1~2回・24回コース
- リハビリ目標
- 装具を軽くして歩けるようになりたい、ギターの弦を抑えられるようになりたい
リハビリの記録
RECORDご利用までの経緯
約1年程前に脳出血を発症され、急性期・回復期病院に約5か月間ご入院。その後はご自宅に退院され、介護保険サービスでの通所リハビリや他社の自費リハビリを併用しながら、懸命にリハビリを継続されてきました。
「装具を軽くして歩きたい」「ギターの弦を抑えられるようになりたい」
そんな前向きな想いから、当センターの無料リハビリ体験にお越しいただきました。現在は、介護保険のサービスと併用しながら、週1~2回のペースで継続的にリハビリをされています。
体験時の状況
体験時は、RAPS-AFO(ふくらはぎ後方に支柱のある下肢装具)と杖を使用し屋内は、なんとか歩行が可能ではありましたが、SPS(足の軽い装具)では内反尖足を止められず歩行が困難でした。
麻痺側の足首(左側)のつま先を下に向ける筋肉(下腿三頭筋や底屈筋群など)が過剰に働きやすく、非麻痺側(右の手・足)に頼った動きのパターンが定着していました。
また、もともとの姿勢の影響や、麻痺側の足の感覚障害により、足元を見ながら歩くことが多くなっていました。
その結果、お腹まわりの筋肉がうまく使えず、頭が前に突き出た姿勢が強くなってしまい、全体の姿勢バランスが崩れていました。
こうした不良姿勢や筋力の低下が、動作中の足首まわりの過剰な緊張(過活動)を引き起こし、バランス機能の低下や歩行機能の低下にもつながっていたと考えられます。
リハビリ内容
左足首の背屈(つま先を上げる動き)の可動域が制限されていたため、可動域改善を行いました。
また、重力の影響が少ない寝た姿勢(臥位)や横向きの姿勢(側臥位)で体幹の筋力を高めることからはじめ、立ち上がりや立位での荷重練習の中で、足と体幹の連動性を改善していきました。
その後、SPSを装着し歩く時の注意点をアドバイスしながら歩行訓練を進めていきました。
リハビリの結果
RESULTそのため歩行時の左足に適切に体重を乗せられる場面が増え、左足での支持が安定することにより右足の一歩一歩が大きく前に出せるようになってきています。
これにより、歩行スピードも改善しました。SPS(足首を支える装具)を使用した歩行では、まだ足の指先が床に引っかかる場面が残っていますが、見守りのもとで安全に歩ける距離が徐々に増えてきています。
担当スタッフからのコメント
COMMENT脳出血の改善事例
CASE







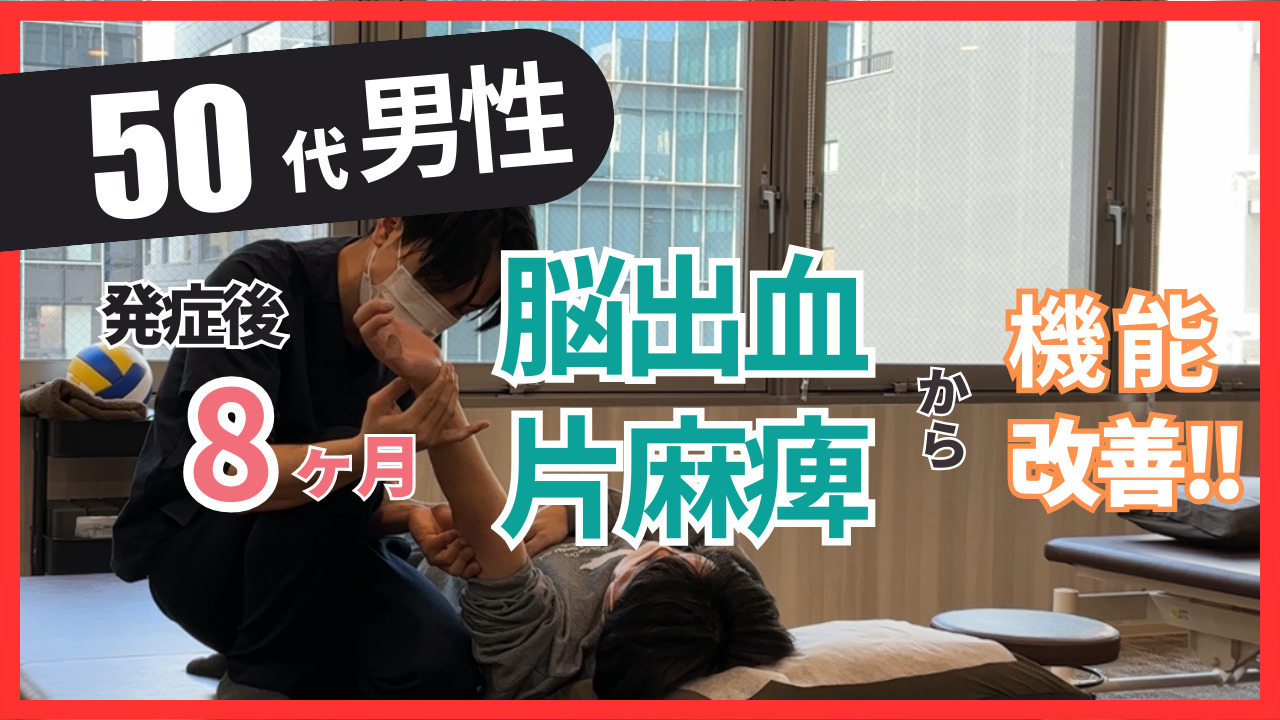

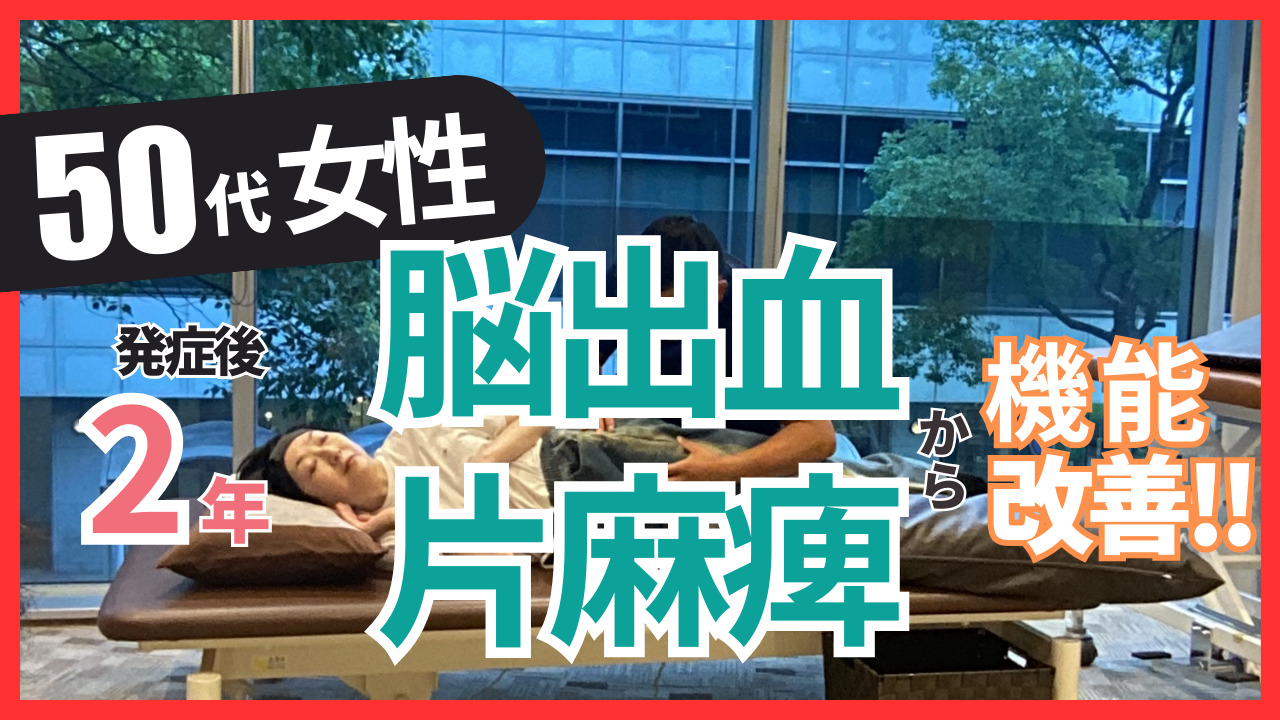
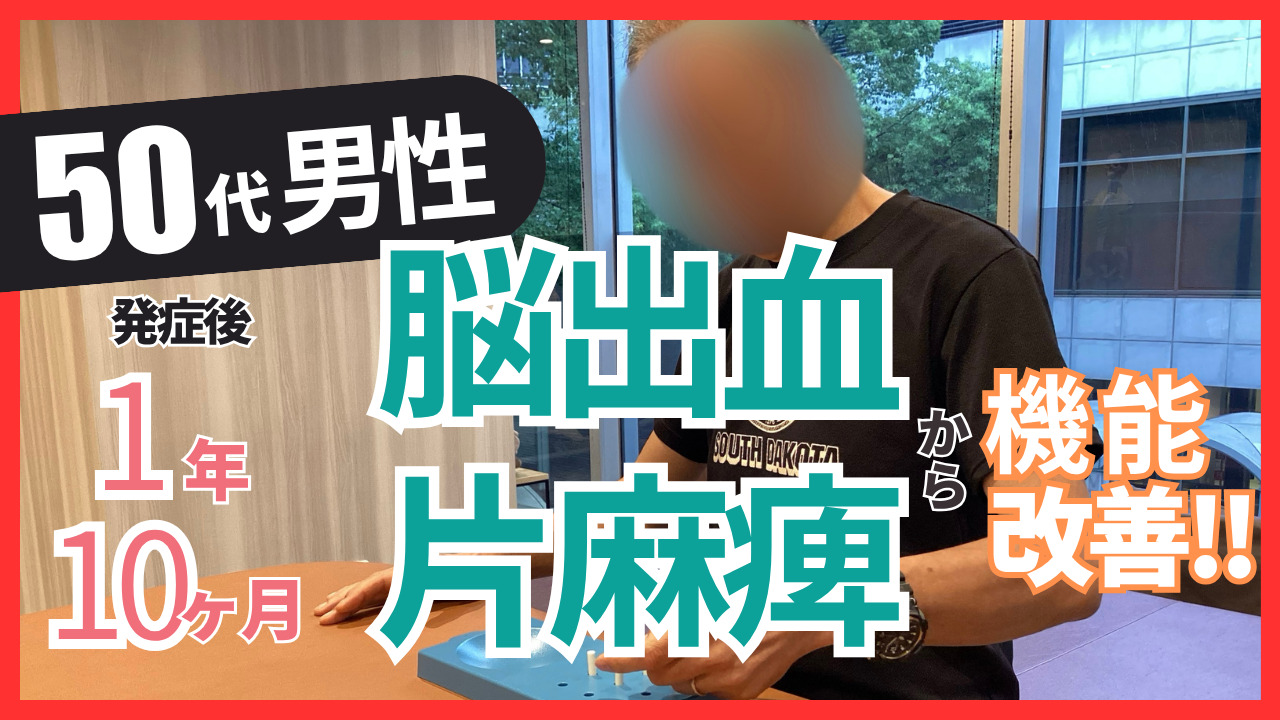




そのため、足首の背屈(つま先を上げる動き)の可動域を広げつつ、体幹機能を改善しバランス機能向上を図りながらリハビリに取り組んだ結果、訓練環境ではSPS(足首の装具)を使って短い距離での歩行が可能になってきました。
今後もリハビリを継続し、屋内ではSPSを使用して歩行が自立できることを目指していきましょう!
目標の歩行が改善してきたら上肢への介入頻度を増やし、実施していきましょう。
市橋 賢