お知らせ
NEWS
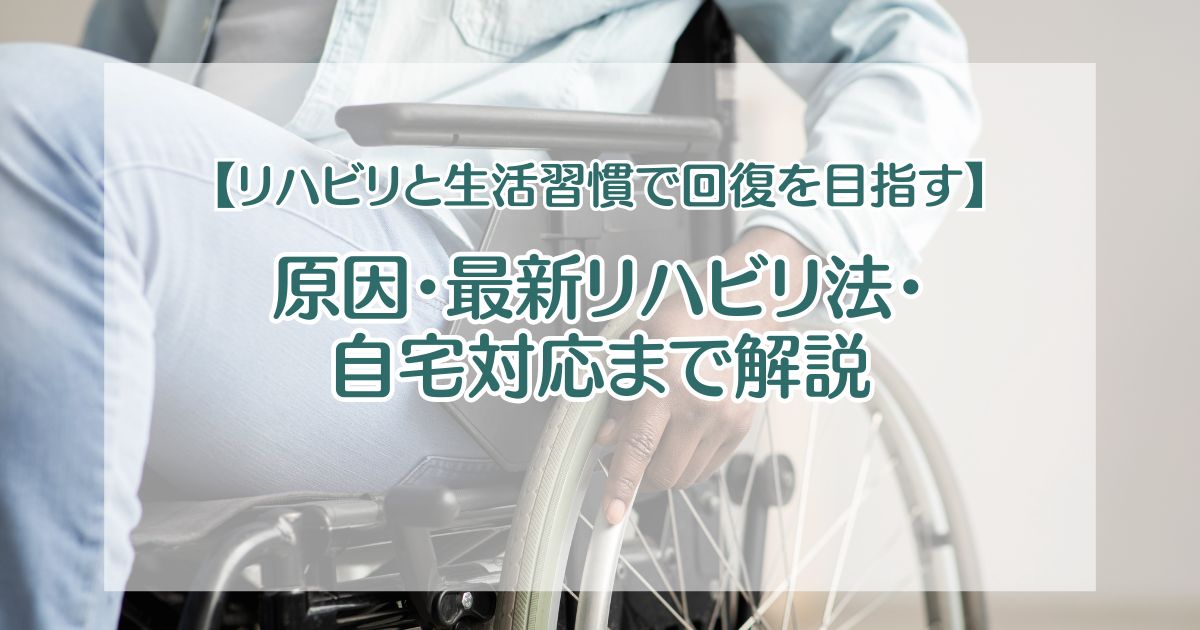

「手が思うように動かない…」そんな不安を抱える患者様・ご家族様へ。
機能が戻らないまま放置すると、日常生活に大きな支障が残る可能性もあります。
この記事では、医学的な原因からリハビリ手法・最新技術・在宅支援策までを専門家が丁寧に解説します。
手の麻痺とは何か|原因と症状

この章では、「手の麻痺」とは何かを正しく理解するために、医学的な定義・原因となる疾患・代表的な症状・経過の変化について詳しくご説明します。
手の麻痺を起こす原因やその進行を知ることで、リハビリの目的や方針が明確になります。
患者様やご家族様が安心して前向きにリハビリに取り組むためにも、基本知識の整理はとても重要です。
手の麻痺とは?|医学的な定義と分類
手の麻痺とは、脳や神経、筋肉の障害によって、手を思うように動かせなくなる状態を指します。
麻痺には次のような分類があります。
- 完全麻痺:全く動かすことができない状態
- 不全麻痺:ある程度は動かせるが、力が入らない、または動作がぎこちない状態
- 片麻痺:体の左右どちらか一方の手足が麻痺している状態
- 末梢性麻痺:神経や筋肉の損傷による麻痺
- 中枢性麻痺:脳や脊髄の損傷によって起こる麻痺
定義を正しく理解することで、リハビリの種類や進め方を適切に選ぶことが可能になります。
主な原因疾患|脳梗塞・脳出血・神経麻痺
手の麻痺の多くは、脳卒中などの神経系の病気が原因です。
- 脳梗塞:脳の血管が詰まり運動機能をつかさどる部分が障害を受けて麻痺が生じる
- 脳出血:脳内で出血が起き、運動機能をつかさどる領域にダメージを与える
- 末梢神経損傷:腕や手を支配する神経が損傷し、麻痺が起きる
- 脊髄損傷:損傷部位の神経経路に障害があると、麻痺が現れる
同じ「手の麻痺」でも、原因が異なれば回復の見込みやリハビリの方法も異なります。
そのため、正確な診断を受けることが第一歩となります。
症状の特徴|運動麻痺・感覚障害・痙縮・変形
手の麻痺には以下のような症状が見られます。
- 運動麻痺:握る、つまむ、持ち上げるといった基本動作ができなくなる
- 感覚障害:触れられた感覚が鈍くなる、温度や痛みを感じにくくなる
- 痙縮(けいしゅく):筋肉が固くなり、手がこわばって開かない
- 変形:指が内側に丸まり、自然な形を保てなくなる
これらの症状は単独で現れることもあれば、複数が重なる場合もあります。
↓↓↓痙縮のコントロールについての詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
【痙縮リハビリガイド】原因・症状別の対策と自費リハでできる改善!
手麻痺の経過|発症初期〜慢性期までの変化
手の麻痺は、時間の経過によって状態が変化します。
適切なリハビリを適切なタイミングで行うことが、回復の鍵を握ります。
- 急性期(発症直後~数週間):腫れや炎症があるため安静が基本。医療機関での治療が優先されます。
- 回復期(数週間~6か月):脳の可塑性(新しい神経ネットワークの形成)を活かし、リハビリの中心的な期間となります。
- 慢性期(6か月以降):改善のペースは緩やかになりますが、継続的なリハビリが機能向上に重要です。
「発症から時間が経ったから手遅れ」ではありません。
どの時期にも適した支援方法が存在しますので、諦めずにご相談ください。
機能回復を目指す基本のリハビリ|理学療法・作業療法の視点から

この章では、急性期から回復期にかけての基本的なリハビリの考え方を解説します。
特に理学療法士・作業療法士が介入するタイミングや目的、自主トレーニングの重要性、そして日常生活動作の回復支援について具体的に紹介します。
リハビリは症状の軽減だけでなく、生活の質(QOL)の向上にもつながります。
急性期〜回復期のリハビリの役割と注意点
リハビリは、発症直後からの介入が回復に大きく影響するとされています。
特に急性期と回復期では、目的と方法に明確な違いがあります。
- 急性期:安静を保ちつつ、関節の拘縮を防ぐポジショニングや可動域訓練を行う
- 回復期:実生活に近い動作訓練や練習によって機能の再獲得を図る
過剰な訓練は逆効果となる場合があるため、専門職による判断が不可欠です。
自主トレーニングの例と注意点
自主トレーニングは、リハビリの効果を継続・促進するうえで重要な役割を担います。
ただし、誤った方法や負荷設定は症状の悪化を招くことがあるため注意が必要です。
- タオルを丸めて握る「グリップ訓練」
- ペットボトルのふたを開ける「巧緻動作訓練」
- 両手でボールを転がす「両側性協調訓練」
症状や目的に合ったトレーニングは、理学療法士・作業療法士と相談の上で選びましょう。
日常生活動作(ADL)での機能改善を目指す
日常生活動作(ADL)とは、食事・着替え・洗顔・トイレ動作などの基本的な生活行動を指します。
ADLの改善は、リハビリの最終的な目標でもあり、機能回復と社会参加に直結します。
- スプーンを使って食事をとる練習
- シャツのボタンをとめる指先訓練
- ズボンの上げ下げなどの着脱動作訓練
生活に直結する動作は、患者様ご自身の生活意欲や達成感にもつながります。
先進的なリハビリ手法
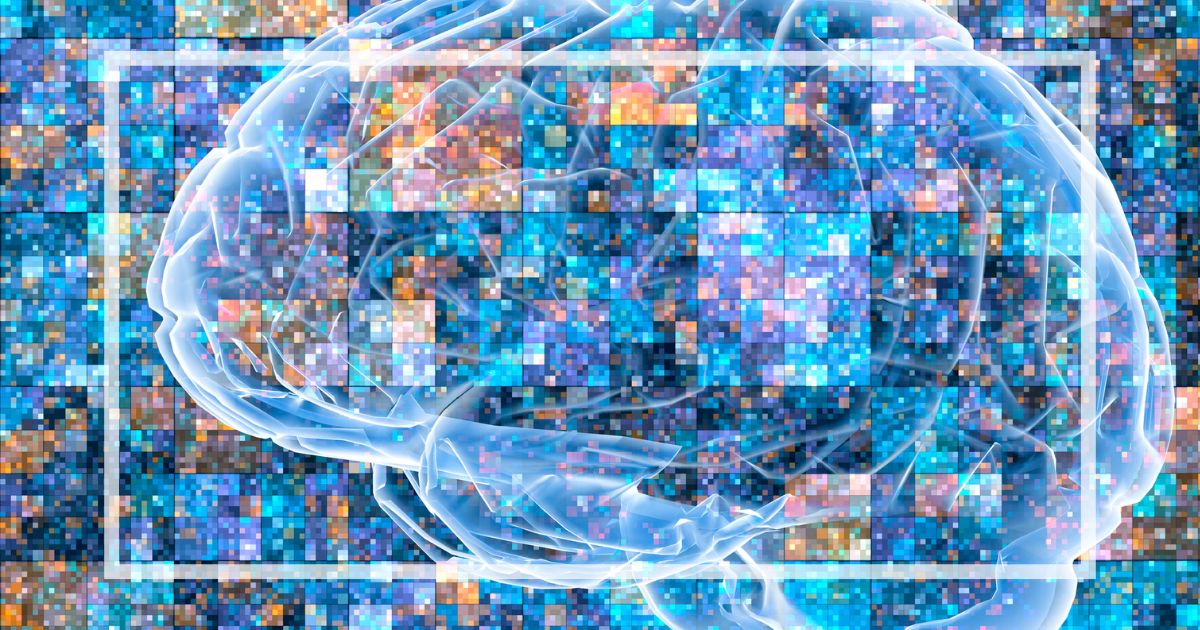
この章では、従来の訓練ではアプローチが難しかった重度の手の麻痺に対し、テクノロジーを活用した最新のリハビリ手法を解説します。
特に注目されているのが、装着型ロボットスーツ「HAL(Hybrid Assistive Limb)」を用いたリハビリです。
脳と筋肉の信号を読み取り、身体の動きを支援・学習することで、回復の可能性を広げる取り組みが進んでいます。
機能的電気刺激(FES)の効果と注意点
FES(Functional Electrical Stimulation)は、筋肉に電気を流して動作を補助する方法です。
麻痺やしびれにより動かしにくい部位に刺激を加え、脳と筋肉の連携を再学習させます。
継続することで、しびれの感覚が和らいでくる例もあります。
- 脳から筋肉への伝達経路を補助し活性化する
- リズムよく反復することで感覚の再構築を促進する
- 設定ミスによる過刺激に注意が必要である
FESは医師の指示と専門家の管理のもとで使用すべき機器です。
3-2. HALを用いたロボットリハビリの可能性と施設の現状
HAL(Hybrid Assistive Limb)は、脳が手を動かそうとした際の生体電位信号を読み取り、動きをサポートする装着型ロボットです。
患者様の意図に応じた動作を支援し、神経系の再教育と自発的な運動学習を促す特徴があります。
- 脳→脊髄→筋肉へ伝わる信号をHALが検出
- 関節運動をHALがアシストしながら反復学習を実施
- 意図的な動作を繰り返すことで、神経回路の活性化を図る
ただし、HALは一部の医療・リハビリ施設での対応に限られているため、導入施設を事前に確認する必要があります。
今後は、HALをはじめとした先端機器を、リハビリプログラムにどう組み込むかが回復への鍵となるでしょう。
在宅でもできるリハビリと補助具の活用

この章では、ご自宅で継続できるリハビリ方法と、補助具やリハビリグッズの効果的な活用法についてご紹介します。
通院が困難な方や、施設でのリハビリが終了した方でも、日常生活に取り入れやすい工夫があります。
患者様の自主性を引き出し、ご家族様の支援とあわせて前向きな生活再建を目指しましょう。
自宅で実践できるストレッチ・巧緻動作訓練
手の麻痺に対しては、柔軟性の維持と繊細な手先の動きを養うトレーニングが重要です。
無理なく続けられる内容を日課として取り入れることが、機能改善への第一歩となります。
- タオルを手で引っ張る「伸展ストレッチ」
- 洗濯バサミを開閉する「指先訓練」
- おはじきをつまんで移す「巧緻動作訓練」
手指に痛みや強いこわばりがある場合は、専門家に相談のうえ実施してください。
手指の拘縮予防とポジショニングの工夫
拘縮とは、関節や筋肉が固まり、可動域が制限される状態です。
発症後から継続的に予防することが、長期的な生活の質を守るために大切です。
- 柔らかいタオルやスポンジを手のひらに丸めて挟む「開排位の保持」
- 寝る・座る際に肘や手首を自然な位置に保つ「ポジショニング」
ご家族様の声かけや見守りも、拘縮予防には効果的です。
装具・スプリント・自助具の選び方と使用法
装具や自助具は、残存機能を活かしながら動作を補助する重要なアイテムです。
選定と使用には注意が必要なため、専門職の指導を受けることが推奨されます。
- 夜間の拘縮予防用スプリント
- 握力補助のためのハンドグリップ
- 箸やスプーンを持ちやすくする自助具
誤ったサイズや目的外使用は、痛みや変形の原因になる可能性があります。
リハビリグッズの活用|おすすめと注意点
市販のリハビリグッズも、在宅訓練の継続に役立ちます。
ただし、使い方や効果を十分に理解して選ぶことが重要です。
- ゴムボールやスポンジ:握力の回復に
- 指のストレッチバンド:屈伸の柔軟性改善に
- リハビリ用タッチパネル:視覚と手の連動を促す訓練に
製品によっては負荷が強すぎる場合もあるため、必ず症状に合わせて選びましょう。
ご家族様ができる支援と見守りのコツ
リハビリの継続には、ご家族様の適度な支援と励ましが不可欠です。
負担を感じさせず、自然な形で日常生活に取り入れていくことが理想です。
- 無理のない声かけやタイミングの工夫
- 成果を小さくても認めるフィードバック
- 一緒に活動することで、孤立感を防ぐ
「頑張って」と繰り返すよりも、「今日はここまでできたね」と寄り添う言葉が力になります。
ご家族様自身のケアや相談の場を確保することも、長期的な支援には大切です。
回復への道を諦めないために|継続の工夫と相談先

この章では、リハビリの継続を支える工夫と、専門的なサポートを得るための相談先の選び方について解説します。
機能回復には時間がかかることもありますが、努力を無駄にしないためにも、継続の工夫と適切な支援体制が必要です。
「もう遅いかも」と思ったときこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
リハビリ継続のコツ|モチベーションと習慣化
リハビリは、継続することで効果が積み重なる取り組みです。
気分が乗らない日もある中で、いかに習慣化するかがポイントとなります。
- リハビリの「目的」を言語化する(例:箸を使って食べたい)
- 小さな目標を設定し、達成ごとに振り返る
- 時間や場所を決めてルーティン化する
ご家族様の温かい励ましや見守りが、継続の支えとなります。
自費リハビリ施設の選び方|費用・内容・専門性
保険内リハビリが終了したあとも、自費リハビリ施設では継続的な支援が受けられます。
施設選びでは、価格だけでなく、提供される内容や専門性を比較検討することが重要です。
- 90分のマンツーマン指導で15,000〜30,000円が目安
- ロボット訓練やFESなど機器の有無を確認
- スタッフが理学療法士・作業療法士などの国家資格を保有しているか
「通える距離にあるか」「自分の症状に合っているか」も忘れず確認しましょう。
↓↓↓自費リハビリの選び方については、こちらの記事をご覧ください。
【料金・頻度・施設選定まで解説!】失敗しない自費リハビリの選び方
改善事例に学ぶ回復のヒント
実際に回復された患者様の事例からは、リハビリの可能性や工夫のヒントが得られます。
同じような症状でも、正しい方法で継続すれば改善につながる例が多数あります。
改善を実感されている方々は、どの方も「続けてよかった」と語っておられます。
小さな成果を重ねることが、大きな一歩になります。
【発症後6年】60代男性・右脳出血の改善事例
退院後は、リハビリサービスをご利用することなくご自宅にて生活、社会復帰されておられました。
歩行では短下肢装具と杖を使用し、屋外を歩行されていました。
リハビリ実施後、体幹の傾きや骨盤の後継が軽減し、上半身の前傾や膝関節の過伸展等の症状も改善しました。
屋内では杖・装具を外して歩行が可能となり、屋外では装具を外し、杖のみで歩行が可能となりました。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【発症後6年】60代男性・右脳出血の改善事例
専門職との連携でリスクを防ぐ|理学療法士・作業療法士の役割
理学療法士や作業療法士との連携は、適切で安全なリハビリを行うために不可欠です。
身体機能だけでなく、生活全体を見通したプランニングが可能となります。
- 現状の評価に基づいた個別プログラムの作成
- 関節や筋肉への負担を防ぐ正しい動作指導
- QOL向上に向けた生活環境の調整提案
独学や自己判断のみでは、かえって悪化させてしまうケースもあります。
迷ったときは、地域の相談窓口やリハビリ専門職に早めに相談することをおすすめします。
まとめ

この記事では、手の麻痺に対する理解とリハビリの実践方法、継続の工夫や相談先までを体系的にご紹介しました。
手の麻痺は、原因や症状、進行具合によって対応が異なりますが、適切な支援と努力を続ければ、機能改善や生活の質の向上が期待できます。
- 麻痺の原因や症状を正しく理解し、段階に応じたリハビリを選ぶことが重要です。
- 在宅でもできるリハビリや補助具の活用で、自主性と生活機能を支えましょう。
- モチベーションを保ち続けるには、ご家族様の支援や専門職との連携が欠かせません。
「もう遅い」と感じる時こそ、再スタートのチャンスです。
どの時期でも、適切なアプローチを重ねていくことで、新たな可能性は広がります。
患者様とご家族様の前向きな一歩を、専門職として心より応援しています。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施
この記事を書いた人

前川 裕樹
作業療法士
2020年に作業療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・外来リハビリ等様々な分野でのリハビリを経験。主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わる。
私は「お客様のご希望を全力でサポートするリハビリ」を常に心掛けております。
お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成を目指します。精一杯のリハビリを実施し、全力でサポート致します。





