お知らせ
NEWS
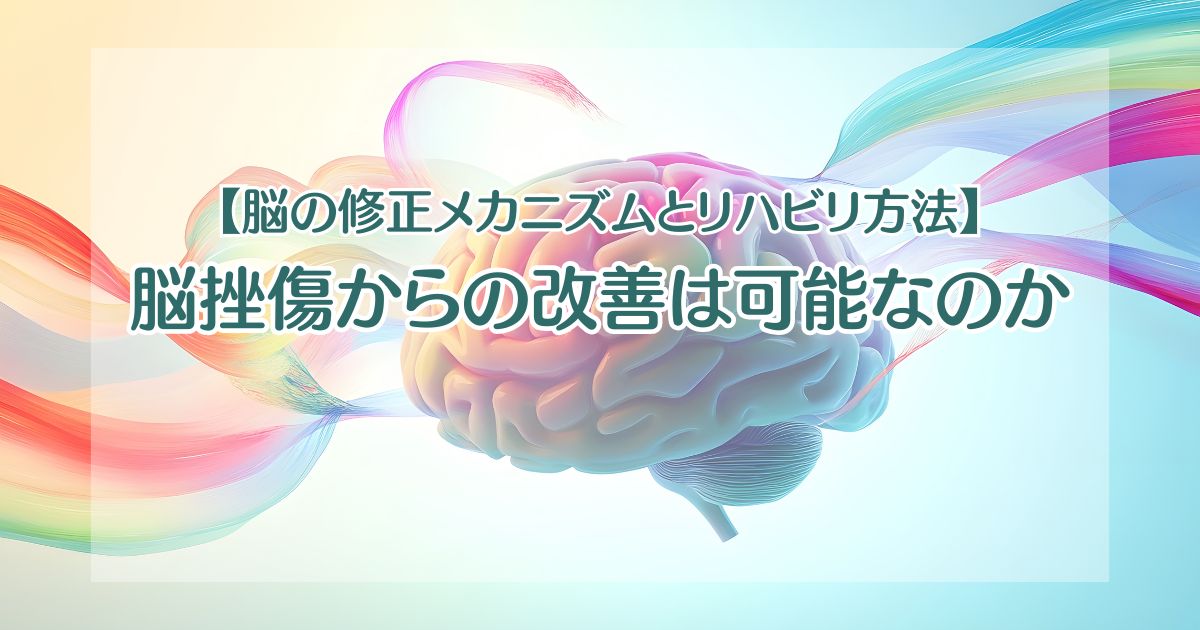

脳挫傷 の後遺症は「改善するのか」と不安を抱える患者様やご家族様は多いのではないでしょうか。
放置すれば生活の質が大きく低下してしまう恐れがあります。
本記事では症状の特徴からリハビリ・制度活用まで解説いたします。
お読みいただき、今後の生活を前向きに考えるヒントとしていただければ幸いです。
1. 脳挫傷とは何か|原因と症状の理解から始めよう

この章では、脳挫傷の基礎的な知識と症状、診断の流れについて解説します。
脳挫傷は、外力によって脳が損傷を受けることで起こる代表的な頭部外傷です。
まずは脳挫傷の仕組みを正しく理解し、改善の可能性を信じるための第一歩を踏み出しましょう。
脳挫傷の定義と発生メカニズム
脳挫傷とは、外部からの強い衝撃で脳の組織そのものに損傷が生じた状態を指します。
「脳震盪」との違いは、脳挫傷では神経細胞や血管の損傷が明確に見られ、画像検査で異常が確認される点です。
損傷の範囲によって、症状は軽度から重度までさまざまです。
脳の一部に出血や腫れ(脳浮腫)が生じる場合もあり、損傷部位によって身体や精神面に影響が出ることがあります。
主な原因と発症のきっかけ
脳挫傷の原因は、日常生活や事故などさまざまな場面で起こり得ます。
特に高齢者や交通事故被害者に多く、現場での対応がその後の回復に大きく影響します。
- 交通事故(シートベルト未着用による頭部の強打)
- 転倒・転落(特に高齢者や階段・浴室での事故)
- スポーツ外傷(サッカー・柔道・ラグビーなどでの衝突)
- 労働災害や転倒事故による頭部打撲
原因が同じでも、衝撃の強さや方向によって損傷部位は異なり、現れる症状も変化します。
そのため、受傷後の早期受診と画像診断が非常に重要です。
初期症状と受傷後の変化
脳挫傷の初期症状は多岐にわたりますが、最も注意すべきは「遅れて悪化するケース」です。
受傷直後は軽い頭痛や吐き気のみでも、数時間後に意識障害が進行する場合があります。
- 意識障害(呼びかけに反応しにくい、昏睡など)
- 頭痛・吐き気・めまいなどの自覚症状
- 記憶障害・集中力低下などの認知面の変化
- 手足の麻痺やしびれといった身体的な異常
受傷直後の変化を観察し、異常を感じた際は早急に医療機関を受診しましょう。
検査・診断方法
診断には、CT検査やMRI検査が主に用いられます。
CTでは脳内出血の有無を確認し、MRIでは脳の微細な損傷を把握します。
また、症状の変化を観察するために入院経過観察を行うケースもあります。
軽度の損傷でも、後に後遺症が出る可能性があります。
そのため、数日〜数週間にわたるフォローアップが必要と言われています。
もし症状が長引く場合は、理学療法士や作業療法士による評価と、適切なリハビリテーション計画が必要です。
早期に専門家へ相談することで、脳機能の改善を最大限に引き出すことができます。
早期に正しい診断と対応を受けることで、二次障害を抑制することができる場合もあります。
安心して次章の「脳の回復メカニズム」へ進み、希望を持って改善の道を学びましょう。
2. 脳挫傷からの回復メカニズム|脳の可塑性が改善を導く

この章では、脳がどのように回復していくのかという仕組みを解説します。
脳は損傷しても、自らの力で再び神経ネットワークを組み替える力を持っています。
「もう治らない」と感じている方も、脳の可塑性を理解することで回復への希望を取り戻せます。
脳の修正メカニズム
- 脳の神経可塑性の促進
脳の神経可塑性とは、経験や学習によって脳が変化し、適応する能力のことです。
リハビリテーションは、脳の神経可塑性、つまり損傷後の脳が新たな神経経路を形成することなどを利用して、機能の再建を促進していく事を目指しています。
積極的なリハビリテーションは、損傷した脳領域の周辺での新たな神経経路の形成を助け、失われた機能の一部を回復させる可能性があります。
しかし、リハビリテーションに一貫性がなければ、その新しい神経接続は十分な繋がりを持てません。
リハビリテーションは、「反復性」と「一貫性」が大切です。
- 機能的回復の最大化
リハビリテーションプログラムは、患者様が失われた運動能力や言語能力を最大限に回復させることを目指します。
リハビリテーションとしては、理学療法、作業療法、言語聴覚療法が必要に応じて実施されますが、患者様一人ひとりに合わせたプログラムであることが大切です。
- 日常生活への再適応
リハビリテーションは患者様が社会に再適応し、自立した生活を送るためのサポートも行います。
回復に影響する主な3つの要因
脳挫傷からの回復スピードには個人差があります。
以下の3つの要因が改善に大きく関係します。
- 損傷部位と重症度:前頭葉・側頭葉など、損傷部位により障害の種類が異なります。
- リハビリ開始のタイミング:早期に取り組むことで、神経回路の再構築が促されます。
- 年齢と意欲:若年層は神経の柔軟性が高く、前向きな姿勢が成果を引き出します。
回復段階とリハビリの焦点
脳挫傷の回復は段階的に進みます。
焦らず、その時期に合ったリハビリを行うことが重要です。
- 急性期(発症〜3か月):生命維持と脳の安定化を図り、早期離床を目指します。
- 回復期(3〜6か月):脳の可塑性が最も高まり、集中的な理学療法・作業療法が効果的です。
- 生活期(6か月以降):生活動作の質を高める段階です。
特に近年、発症半年以上経過した方でも上肢機能の改善や日常生活動作の改善を認める先行研究が出てきています。
必要に応じて、自費リハビリなど長期的な支援を活用しましょう。
まとめ:
脳の可塑性は年齢を問わず、どなたにも備わる力です。
焦らず継続的にリハビリを行うことで、脳は新たな経路を作り、回復への道を切り開きます。
3. 脳挫傷後に起こりやすい後遺症と改善のアプローチ

この章では、脳挫傷によって起こりやすい後遺症と、その改善を目指すリハビリ方法について解説します。
脳挫傷の後遺症は、身体面だけでなく思考や感情面にも影響を与えることがあります。
二次障害の影響を減らすためにもリハビリは必要です。
高次脳機能障害(記憶・注意・思考)
脳の前頭葉や側頭葉が損傷を受けると、記憶や判断、注意の維持が難しくなることがあります。
これを高次脳機能障害と呼びます。
たとえば「話している途中で内容を忘れる」「予定を立てても実行できない」などが見られます。
改善には、チーム医療で連携した認知リハビリが効果的です。
以下のような訓練が行われます。
- メモやスケジュール帳を活用した記憶補助訓練
- パズルや言語課題による注意・集中力トレーニング
- 買い物や調理など、実際の生活場面を想定した遂行機能訓練
注意:一度に多くの課題を与えると混乱を招く恐れがあります。
少しずつ成功体験を積み重ねることが大切です。
身体機能障害(麻痺・歩行・手の動作)
脳挫傷では、麻痺や筋緊張の変化が生じることがあります。
理学療法士や作業療法士は、運動機能の改善を目指した訓練を段階的に行います。
- 関節可動域訓練(関節の硬さを防ぐ)
- 筋力維持・改善のための抵抗運動
- 歩行・バランス訓練(重心移動の再学習)
- 動作訓練(起き上がり・立ち上がり・衣服の着脱など)
訓練の過程で疲労や痛みが出ることもありますが、適切な休息を取りながら継続することで効果は高まると言われています。
平衡機能・感覚の障害
頭部の打撲によって、平衡感覚をつかさどる小脳や前庭系が影響を受けることがあります。
その結果、立ち上がりや方向転換が不安定になるケースが見られます。
- 前庭リハビリ(眼球運動・頭部運動訓練など)
- 感覚刺激療法(触覚・圧覚を用いた再教育など)
- 立位保持訓練やバランス訓練など
平衡感覚の改善には、反復練習と安全な環境づくりが重要です。
ご自宅で行う場合は、転倒防止のための手すりや滑り止めマットを併用しましょう。
外傷性てんかん・頭痛などの二次症状
脳挫傷後には、数か月〜数年後に外傷性てんかんが発症することがあります。
また、慢性的な頭痛や倦怠感に悩まされる方も少なくありません。
これらの症状は、医師の管理下での薬物治療とリハビリの両立が重要です。
生活面では、十分な睡眠・規則的な生活・ストレス軽減が再発予防に効果的です。
症状が強い場合は、医師・理学療法士・作業療法士が連携して支援します。
諦めずに小さな変化を積み重ねていくことが、回復への近道です。
まとめ:
脳挫傷後の後遺症は多様ですが、専門職によるリハビリで改善の可能性を高めることができます。
焦らず、今できることを一歩ずつ積み重ねていきましょう。
4. 改善を促すリハビリと最新の取り組み

この章では、脳挫傷からの回復を支えるリハビリの内容と、最新の取り組みについて解説します。
近年はAIやロボット技術を活用した新しいリハビリも登場し、改善の可能性が広がっています。
理学療法・作業療法の役割
脳挫傷後のリハビリでは、理学療法士と作業療法士が中心的な役割を担います。
理学療法士は身体機能の回復を、作業療法士は日常生活動作や社会復帰を支援します。
- 理学療法(PT):姿勢・歩行・バランス訓練を通じて、筋力や可動域の改善を図る。
- 作業療法(OT):着替え・食事・書字などの動作を訓練し、生活の自立を目指す。
- 言語聴覚療法(ST):発話・嚥下・コミュニケーション能力を高める支援。
各専門職が連携することで、身体面だけでなく、認知・社会的側面の改善も期待できます。
先進的なリハビリ技術(HAL®・AI訓練・ロボットリハ)
近年、テクノロジーを活用したリハビリが進化しています。
特に、HAL®(Hybrid Assistive Limb)は日本発の装着型ロボットで、筋肉の微弱な電気信号を検出して動作をサポートします。
AI搭載のリハビリ機器では、動作データをもとに最適な運動プランを自動で提案できます。
これにより、理学療法士の指導を補完し、より効率的な訓練が可能になります。
ただし、すべての患者様に適応するわけではありません。
導入には医師やリハビリ専門職の評価が必要です。
自費リハビリ施設の特徴と選び方
医療保険や介護保険ではリハビリ期間に制限がありますが、自費リハビリはその制約を受けません。
「もっと良くなりたい」と願う方にとって、再チャレンジの場となります。
- 保険に制限されないため、必要な期間・頻度で通える。
- 90分など長時間の個別リハビリで、集中した訓練が可能。
- 先進機器やマンツーマン指導など、質の高いサポートを受けられる。
施設を選ぶ際は、理学療法士・作業療法士が在籍しているか、脳神経リハビリの専門性があるかを確認しましょう。
また、実際に体験利用を行い、訓練内容や雰囲気を確かめることも重要です。
患者様一人ひとりに合った方法を選び、改善への一歩を踏み出しましょう。
↓↓↓自費リハビリの選び方については、こちらの記事をご参照ください。
【料金・頻度・施設選定まで解説!】失敗しない自費リハビリの選び方
リハビリは単なる回復の手段ではなく、患者様とご家族様が安心して生活を続けるための伴走者となります。
適切な支援を受けることで、諦めずに社会参加を目指すことができます。
脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。
【発症後3年9ヶ月】60代・男性・くも膜下出血の改善事例
ご自宅退院後は、通所リハビリや鍼灸など色々試されていましたが、歩行能力の改善・杖歩行の獲得が諦めきれず
HPよりお問い合わせを頂き、無料体験を実施後に当施設ご利用開始となりました。
そんな前向きな想いから、当センターの無料リハビリ体験にお越しいただきました。
現在は、介護保険のサービスと併用しながら、週2回のペースで継続的に通所されています。
体験時は、左足(麻痺側)力の入れ方・体重の支え方・バランスのとり方がわからず全身に過剰に力が入っていました。
リハビリ4回目時点で、ご本人様より『ここに力を入れると立ちやすい・歩きやすい』などといった反応がみられてきました。
ご利用10ヶ月目には、ほぼ見守りで10-20m程の杖歩行が可能となってきました。
徐々に麻痺側の足で体重を支えることができるようになってきた為、バランス能力の向上をみとめ歩行時のワイドベースが減ってきています。
さらに、最近では杖なしの歩行練習にチャレンジできるほどになってきました。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【発症後3年9ヶ月】60代・男性・くも膜下出血の改善事例
5. 回復を支えるご家族様の関わりと心のケア

この章では、脳挫傷からの回復を支えるご家族様の関わり方と、心のケアの重要性について解説します。
脳挫傷の回復には、医療やリハビリだけでなく、ご家族様の理解と支えが欠かせません。
ご本人様の変化を受け止めながら、一緒に歩む姿勢がリハビリの成果を左右します。
ご家族様が理解しておきたい回復のプロセス
脳挫傷の回復は、直線的に良くなるわけではなく、「良い日と悪い日の波」を繰り返すことが一般的です。
回復期には、疲労や情緒の揺らぎが見られることもあります。
- 昨日できた動作が、今日は難しくなることがある。
- 新しい刺激に慣れるまで時間がかかる。
- 精神的な落ち込みが一時的に強くなる。
このような変化は、脳が再び神経ネットワークを組み直しているサインです。
焦らず、ゆっくりと見守ることが大切です。
また、ご本人様が自立したい気持ちを尊重し、できることを奪わないようにしましょう。
在宅でできる環境調整とコミュニケーション
在宅生活を安全に続けるためには、生活環境の工夫が欠かせません。
転倒や動作の負担を減らすための環境調整は、理学療法士や作業療法士の助言のもとで行うとより効果的です。
- 床の段差をなくす、カーペットの滑り止めを設置する。
- 手すりの設置や、必要に応じた福祉用具の導入。
- 動線を短くし、トイレや寝室のアクセスを安全にする。
また、コミュニケーションの取り方も重要です。
感情の起伏や言葉の理解に時間がかかる場合は、ゆっくり・短く・肯定的に話しかけることを意識しましょう。
心理的負担への支援と相談窓口
脳挫傷のリハビリは長期戦です。
ご家族様も心身の疲労を抱えやすく、知らず知らずのうちにストレスが蓄積することがあります。
そのままにしておくと、介護うつや家庭内不和につながる恐れもあります。
- 地域包括支援センター:介護・医療・生活相談を一括でサポート。
- 医療ソーシャルワーカー:経済的支援や制度利用の相談窓口。
- 家族会・ピアサポートグループ:同じ経験を持つ人とつながり、気持ちを共有できる。
無理をせず、相談できる人や場所を見つけておきましょう。
まとめ:
脳挫傷からの回復は、ご本人様とご家族様の二人三脚で進むプロセスです。
支える側も一人で抱え込まず、専門職や地域のサポートを上手に活用することで、前向きに歩み続けることができます。
6. まとめ|希望を持ち続けることが脳を変える

脳挫傷からの回復は、時間のかかる挑戦です。
しかし、脳の可塑性とリハビリの力を信じ、希望を持ち続ける姿勢こそが改善の力となります。
回復への道を一歩ずつ進む
リハビリは小さな積み重ねの連続です。
一日一日の訓練が神経の再結合を促し、確実に変化をもたらします。
成果がすぐに見えなくても、継続することが回復の鍵です。
専門家と共に歩む安心感
理学療法士や作業療法士は、患者様一人ひとりに合わせた最適な支援を提供します。
回復期を過ぎても、適切な目標設定と専門的サポートがあれば、生活の質を高め続けることが可能です。
ご家族様と共に支え合う回復
ご家族様の理解と支えが、患者様の心の安定を支えます。
一緒に前向きに取り組む姿勢が、リハビリの継続意欲を高める力になります。
専門家と共に、一歩ずつ前に進む気持ちを忘れずに歩んでいきましょう。
最後に:
脳挫傷からの回復は、諦めずに取り組むすべての方に開かれた道です。
焦らず、希望を持ち、歩み続けることで、きっと「できること」が増えていきます。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

水谷 滉希
理学療法士
2017年に理学療法士免許を取得。同年より理学療法士として勤務。一般病棟、地域包括病棟、回復期病棟、外来リハビリ、訪問リハビリ等様々な分野でのリハビリを経験。
2022年には名古屋市内の回復期病棟立ち上げをチームリーダーとして携わる。2023年10月脳神経リハビリセンター名古屋に勤務。
私は常に「諦めない気持ち」を大切にしています。セラピストとお客様が二人三脚となり、最後まで諦めず目標達成を目指しています。全力でサポートさせて頂きます。目標達成に向けて一緒に歩んでいきましょう。





