お知らせ
NEWS
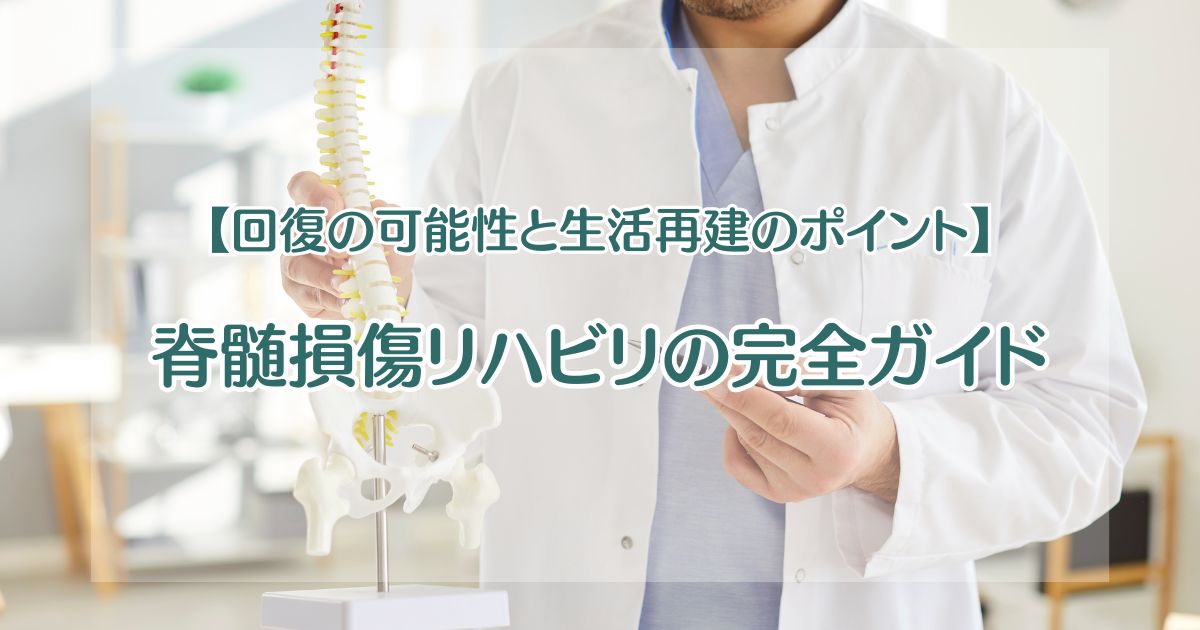

脊髄損傷後の生活は、歩行や排泄など日常の自立に大きな壁が立ちはだかります。
「もう元の生活には戻れないのでは」と不安を抱える患者様・ご家族様も少なくありません。
適切なリハビリを行わなければ、機能低下や社会復帰の遅れにつながる恐れがあります。
本記事では、急性期から在宅期までのリハビリ内容と専門職の役割をわかりやすく解説します。
生活の再建に向けた具体的な一歩見出していただければ幸いです。
脊髄損傷とリハビリの基礎知識

脊髄損傷とは?症状と生活への影響
この章では、脊髄損傷の基礎知識と生活への影響について説明します。
脊髄損傷とは、背骨にある脊髄が損なわれることで運動や感覚に障害が生じる状態を指します。
症状は損傷の部位や程度によって異なり、歩行の困難さや排泄の問題などが現れることがあります。
- 歩行障害や車いす生活への移行
- 排泄や入浴など日常生活動作(ADL)の制限
- ご家族様による介助の必要性
これらの影響は身体機能だけでなく、心理的・社会的な側面にも及びます。
しかし適切なリハビリを行うことで、自立度を高めることが可能です。
リハビリの目的|生活の自立・機能維持・社会復帰
ここではリハビリの目的を整理します。
脊髄損傷のリハビリは「失った機能を補い、残された力を最大限に活かす」ことが中心です。
特に重要な目的は次の3点です。
- 生活の自立:着替えや移乗、排泄などを自分で行えるようにする
- 機能維持:残存している筋力や感覚を保ち、悪化を防ぐ
- 社会復帰:就労や趣味活動を再開し、生活の質を高める
リハビリの頻度が減ることで、筋力低下や関節の固さ(拘縮)が進行し、日常生活の負担が大きくなります。
一方、リハビリを継続すれば、患者様の自立度が上がり、ご家族様の介護負担も軽減されます。
リハビリ開始のタイミングと重要性
リハビリは受傷後の早期から始めることが大切です。
早期に体位変換を行うことや関節を動かす練習を行うことで、褥瘡や拘縮を予防することができます。
また早期介入を行うことで、残存機能をより効率的に引き出すことが出来ます。
状態が落ち着いた時点で、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士が患者様に合わせた計画を立て、段階的に支援を進めていきます。
適切な計画立てることで、患者様は、生活の自立や社会復帰への道筋を早く描けるようになります。
リハビリの段階と専門的支援

急性期|体位変換・呼吸訓練・関節可動域訓練
この章では、脊髄損傷リハビリの段階と専門的支援を説明します。
前章でもお伝えした通り、急性期は受傷直後の状態を安定させることが最優先です。
同時に、合併症を予防するための基本的なケアも大事になってきます。
- 体位変換:長時間同じ姿勢を避け、床ずれを防ぐ
- 呼吸訓練:呼吸筋の働きを支え、肺炎リスクを軽減する
- 関節可動域訓練:関節が固まる「拘縮」を予防する
急性期からの小さな取り組みを行うことが、その後の経過に大きく影響します。
回復期|歩行・移乗・筋力強化のアプローチ
全身状態が安定すると回復期でのリハビリが始まります。
この時期は実際の生活に必要な動作を取り戻すことが中心です。
歩行練習や車いす移乗の訓練を繰り返すことで、動作の自立を目指します。
- 歩行訓練:装具や歩行器を使用し、残存機能を活かす目的で実施
- 移乗訓練:ベッドから車いす、トイレなどへ安全に移る方法を習得する
- 筋力強化:残された筋力を維持し、生活動作の安定につなげる
適切な運動強度を守ることで、痛みや疲労を防ぎ、効果的にリハビリをすすめることが出来ます。
理学療法士や作業療法士の指導のもとで安全に進めることが大切です。
在宅生活期|自宅でのリハビリと生活動作の工夫
退院後の在宅生活期は「できることを続け、生活に組み込む」ことが重要です。
筋力や柔軟性は使わなければ低下するため、継続的なリハビリが必要となります。
ご家族様と一緒に無理のない範囲で体を動かす習慣を作ることが効果的です。
さらに車いす操作の工夫や住宅改修を取り入れると、行動範囲が広がり活動性が維持されます。
専門職の役割|理学療法士と作業療法士の違い
リハビリにはいくつかの段階があり、それぞれの段階を支えているのが専門職です。
理学療法士は歩行や移動といった身体機能の回復を支援します。
一方、作業療法士は食事や排泄、家事動作など日常生活の再建に焦点を当てます。
また、言語聴覚士は「話す・聞く・食べる」を助ける専門家になります。
- 理学療法士:歩行・姿勢・筋力維持など身体機能に特化
- 作業療法士:日常生活動作や社会参加を中心にサポート
- 言語聴覚士:話すことや聞くこと、食べることをサポート
それぞれの専門職の協力があることで、患者様は生活全体を見据えたリハビリを受けることが出来ます。
これにより、ご家族様の介助負担も軽減され、安心した生活の再構築が可能になります。
日常生活を取り戻すためのリハビリの内容

移動手段の確立|歩行練習・車いす操作訓練
この章では、日常生活を取り戻すためのリハビリを解説します。
まず大切なのは、移動手段の確立です。
患者様に残された機能を活かし、それに合わせた装具や補助具を選定します。
そのうえで歩行練習や車いす操作の練習をすることで、行動範囲は広がります。
- 歩行練習:装具や歩行器を使用し安全で効率的な歩行を学ぶ
- 車いす訓練:坂道・段差など生活環境を想定し、行動範囲を広げる目的で行う
移動手段の自立は「外出できる安心感」を生み、心理面の回復にもつながります。
上肢・手指機能の改善に向けた取り組み
脊椎損傷では手や腕の動きに障害が残ることがあります。
上肢や手指のリハビリを進めることで、食事や身支度といった生活の基盤を取り戻せます。
作業療法士が中心となり、細かな動作の練習を行います。
患者様自身でできる動作が増えれば、ご家族様の介助負担も軽減できます。
摂食・排泄・入浴などADL(日常生活動作)の支援
リハビリは食事・排泄・入浴といった基本的な生活動作の改善にもつながります。
ADLとは「Activities of Daily Living(日常生活動作)」の略で、生活の質を測る大切な指標になります。
自立度を高めるためには、動作の工夫や補助具の活用による環境整備が重要になってきます。
- 摂食:自助具の工夫や座位保持の安定化のための工夫
- 排泄:ポータブルトイレやトランスファーボードの活用
- 入浴:シャワーチェアや浴室手すりの設置
環境整備が不十分だと、ADLが改善されず、自分で生活する力が弱まります。
その結果ご家族様や他の第三者のサポートが必要な場面が増えてしまいます
逆に環境整備を工夫すれば「できること」が増え、自信の回復にもつながります。
ご家族様ができる介助方法と介護負担の軽減
日常生活を取り戻すためには、ご家族様の支えが重要です。
ただし無理な介助は身体的負担やストレスにつながるため、正しい方法を学ぶ必要があります。
介助方法を習得することで、安全性と効率性を両立できます。
- 移乗介助:腰を痛めないよう姿勢を工夫する
- 更衣介助:一方向から順序立てて衣服を着脱する
- 排泄介助:介助用具を使いご家族様の負担を軽減する
専門職と連携しながら進めることで、患者様の自立とご家族様の安心が両立できます。
こうした取り組みは、在宅での生活を安定させる大きな力となります。
社会復帰を見据えたサポート

福祉用具・自助具の選び方と活用法
この章では、社会復帰を目指すために必要な支援を解説します。
まず重要なのは福祉用具や自助具の活用です。
患者様の残存機能に合わせた用具を導入することで、生活動作の幅が大きく広がります。
- 車いすや電動アシスト付き車いす
- シャワーチェアやトランスファーボード
- 自助具(特殊なスプーン・箸・衣服補助具など)
適切な用具を取り入れることで、自立度を高めると同時にご家族様の負担も軽減されます。
住宅改修・生活環境調整のポイント
在宅生活を送る上で、住宅改修や環境調整は欠かせません。
段差や浴室の安全性を見直すだけでも転倒リスクを減らせます。
また、介助者にとっても動線がスムーズになり介助が容易になります。
このような改修は補助制度が利用できる場合もあるため、専門職に相談することをお勧めいたします。
就労・学業・余暇活動の再開に向けた支援
社会復帰とは、就職や復職、学校への復学だけでなく、趣味や地域活動などの余暇を楽しむことも含まれます。
それらの活動において体力や集中力を保つことは難しいですが、少しづつでもいいので段階的に活動量を上げていくことが大切です。
理学療法士や作業療法士は、実際の場面を想定した練習をサポートします。
- 職場復帰に向けた通勤練習や勤務時間の調整
- 学業再開に備えた集中力や姿勢保持のトレーニング
- 趣味やスポーツ活動を取り入れた生活リズムづくり
ご本人の状態に合わない無理な活動を行うことは、体調の悪化や再受傷のリスクを高める可能性がありますので、注意が必要です。
焦らず計画的に進めることが、長期的な社会参加を行うことにつながります。
ピアサポート|先輩患者様との交流の効果
社会復帰を目指す上で欠かせないのがピアサポートです。
ピアサポートとは、同じ障害経験を持つ先輩患者様が支援する取り組みを指します。
共通の経験を通じた交流は、精神的な励みとなり、孤独感を和らげます。
- リハビリ継続へのモチベーションが高まる
- 日常生活で役立つ工夫を具体的に学べる
- ご家族様も安心できる交流の場になる
ピアサポートは「自分にもできる」という希望を与え、社会参加を現実的な目標に変えてくれます。
結果として、患者様・ご家族様の生活がより前向きなものとなります。
脊髄損傷リハビリの可能性とこれから

改善の可能性とその目安
この章では、脊髄損傷リハビリの将来性と可能性を解説します。
改善の度合いは損傷の部位や重症度によって異なりますが、早期から適切に取り組むことで多くの機能を維持することができます。
「完全に治るのか」という不安は大きいですが、現実的には残存機能を最大限に引き出すことが重要な目標です。
- 受傷後3か月:神経の回復が最も期待できる時期
- 半年以降:新しい生活動作の習得が中心となる時期
- 1年以降:リハビリ継続により生活の安定を目指す時期
「一定期間を過ぎると回復は不可能」と誤解されがちですが、実際には長期的な努力で改善が見られる方もおられます。
継続するための工夫|モチベーション維持
リハビリは長期間にわたるため、途中で意欲が低下することもあります。
継続のためには、日常生活の中に小さな目標を設定することが効果的です。
「今日はベッドから車いすへ自分で移動できた」といった成功体験が大きな目標を達成するための力になります。
- リハビリの成果を日記やアプリで記録する
- ご家族様と一緒に取り組み、お互いに励まし合う
- ピアサポートに参加し、先輩患者様の工夫を学ぶ
小さな達成感を積み重ねることで、継続意欲を守りやすくなります。
自費リハビリや先進的アプローチの活用(例:ロボットリハビリ)
近年では医療保険や介護保険の枠にとらわれない自費リハビリの利用が注目されています。
特にロボットリハビリや電気刺激療法など先進的な方法は、従来のリハビリでは難しかった疾患の改善を補完する可能性を持っています。
これらは医学的な根拠に基づき導入が進められており、患者様の選択肢は広がりました。
ただし、一般の病院で導入しているところは少なく、主に難病指定などがある方に適用されます。
自費リハビリでは禁忌事項に該当しなければ疾患を選ばず使用できるといったメリットがある反面、費用面の負担があります。
そのため、ご利用の際はご家族様と相談し、継続できる体制を整えることが重要です。
今後のリハビリは「従来の基本訓練」と「先進的技術」を組み合わせ、より幅広い回復の可能性を追求する方向に進んでいます。
患者様・ご家族様にとっても、将来を前向きに描けるサポート体制が整いつつあります。
5-3. 自費リハビリ施設を利用するメリットと注意点
自費リハビリでは、医療保険や介護保険の枠にとらわれず、集中的なリハビリを行うことが可能です。
- 保険制度外でも、リハビリ時間や頻度を柔軟に設定できる
- 専門職によるマンツーマン指導が受けられる
- 機能改善を目的とした集中プログラムが組まれる
費用は全額自己負担です。継続できる計画と目的を明確に持つことが大切です。
脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。
希望をもって一歩を踏み出していただくため、実際にリハビリを行った方の事例を紹介いたします。
【発症後約4年】30代・女性・脊髄損傷(不全麻痺)の改善事例
それからは主にベッド上での生活が続きましたが、「もう一度、自分の足で立ちたい」という強い想いから、当施設の無料リハビリ体験にお越しいただきました。
その後は週1回のペースで継続的にリハビリに取り組まれています。
当施設でのリハビリを開始されわずか約1か月程度経過した時点で大きな変化が現れました。
介助が必要だった起き上がり動作がお一人で可能となり、座位保持も見守りで可能となりました。
また、ご利用当初は、HALを使用しても足の筋力はわずかにしか出現しませんでしたが反復し行うことで少しずつ筋肉の収縮を感じられるようになってきました。
ご本人様からも少しずつだが『足に力が入る気がする』との前向きなお声をいただいております。
さらにリハビリを通して、体が少しずつ動き始めたことで、リハビリ中の笑顔も増えてきました。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【発症後約4年】30代・女性・脊髄損傷(不全麻痺)の改善事例
↓↓↓自費リハビリの選び方については、こちらの記事をご参照ください。
【料金・頻度・施設選定まで解説!】失敗しない自費リハビリの選び方
まとめ|諦めずに生活の幅を広げるために

脊椎損傷のリハビリは、一朝一夕で成果を出すことは難しいですが、取り組み次第で生活の質を大きく改善できます。
急性期から維持期まで、それぞれの段階で適切な支援を受けることが重要です。
また理学療法士や作業療法士、言語聴覚士と連携することで、日常生活や社会復帰への準備が進めやすくなります。
- 残存機能を最大限に活かすことが大切
- 継続的なリハビリで生活の安定を得られる
- ご家族様と専門職が協力することで介助負担を軽減できる
- 自費リハビリや先進技術を取り入れると選択肢が広がる
「もうできない」と諦めるのではなく、工夫と支援を重ねることで生活の幅は大きく広がります。
リハビリを通じて身体の改善だけではなく、患者様やご家族様の心の安心にもつながります。
将来に向けて希望を持ち続けることは決して無駄ではありません。
小さな前進を積み重ねることが、社会参加や自立への大きな一歩となります。
この記事が、今後のリハビリに取り組む皆様の道しるべとなれば幸いです。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

細葉 隆
理学療法士
2006年に理学療法士免許を取得。
一般病院・訪問リハビリ・介護老人保健施設・通所リハビリと全てのステージで脳卒中を中心としたリハビリを経験。
2024年、公的保険で回復できなかったお客様の改善をしたいという想いから、脳神経リハビリセンター仙台に勤務。
私はこれまでに様々なお客様とそのご家族とリハビリを通して関わってきました。お客様の夢や目標に向かってチームとして、そしてセラピストとして携わってきました。私のモットーはお客様や家族の方と同じ方向を向き、寄り添いながら一緒に進んでいくことです。
脳神経リハビリセンターでは、充分な時間と最新の機材が整っており、リハビリを必要としている方の夢を叶える場所であると確信しています。
1回1回のリハビリを通じて、小さな変化や気付きに喜びを分かち合い、目標が達成に向けて一緒に頑張ってみませんか。
皆様との出会いを楽しみにしています。





