お知らせ
NEWS
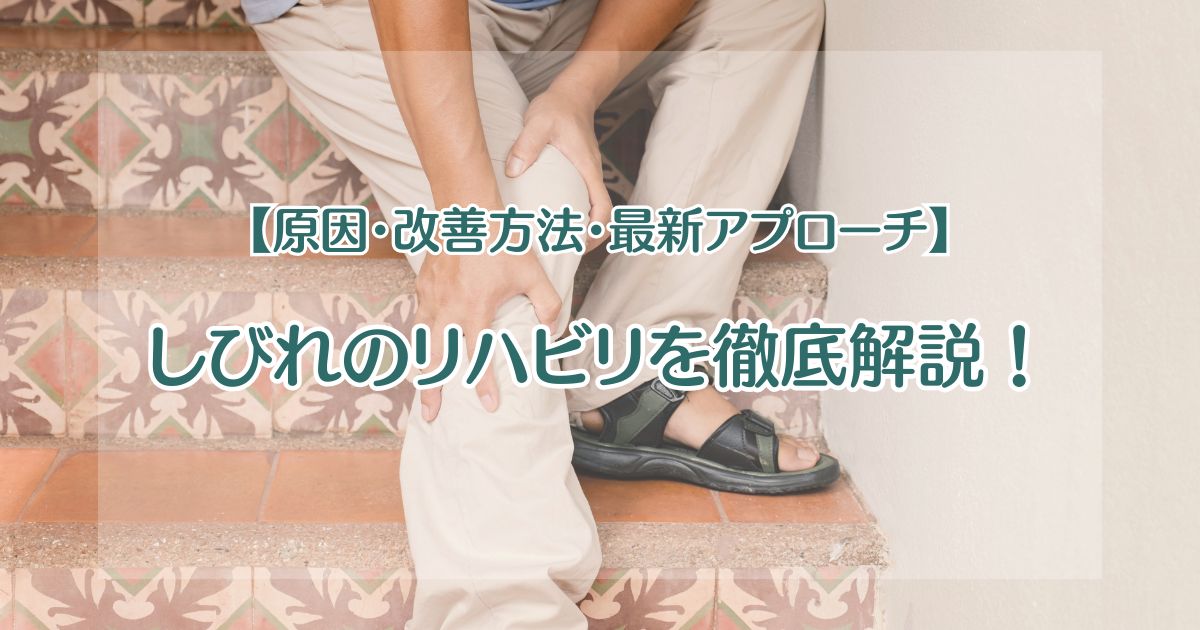

手足のしびれが続き「治るのか不安」と悩んでいませんか?
本記事では、しびれの原因・リハビリ方法・最新アプローチをリハビリ専門職の視点で解説します。
お読みいただいた方の、しびれ改善の一助となれば幸いです。
しびれとは何か|原因と症状の正しい理解

この章では、しびれの定義や医学的な位置づけを整理し、脳卒中後や末梢神経障害など原因別の特徴を解説します。
さらに、麻痺との違いを明確にし、患者様やご家族様が正しく理解できる基礎知識を提供します。
しびれの定義と医学的な位置づけ
しびれとは、皮膚や筋肉で感じる感覚が通常と異なり、「ジンジンする」「ピリピリする」と表現される状態です。
医学的には「感覚障害」の一種に分類されます。
脳や脊髄の障害、神経の圧迫、血流の低下など、発生要因は複数あります。
- 長時間同じ姿勢での神経圧迫
- 脳卒中や外傷による中枢神経の障害
- 糖尿病や生活習慣病に伴う末梢神経障害
一時的なしびれは自然に改善しますが、持続する場合は病気のサインです。
脳卒中後のしびれの特徴とメカニズム
脳卒中後にみられるしびれは、中枢神経が損傷することにより起こります。
脳の感覚を司る領域が障害を受けると、身体の一部に持続的なしびれが残ることがあります。
このしびれは血流障害による一時的なものではなく、神経の再生や可塑性に時間がかかる点が特徴です。
リハビリでは神経の再学習を促すことが重要です。
↓↓↓脳梗塞によるしびれのリハビリについては、こちらの記事をご覧ください。
【改善策をリハビリの専門職が解説!】脳梗塞後のしびれは治るのか?
末梢神経障害や姿勢不良によるしびれとの違い
末梢神経障害によるしびれは、糖尿病性神経障害や手根管症候群などで起こります。
これらは手先や足先から症状が始まりやすい点が特徴です。
一方、長時間の不良姿勢は神経や血管を圧迫し、一時的なしびれを引き起こします。
しびれと麻痺の違いを整理する
しびれは「感覚」に関する異常であるのに対し、麻痺は「運動」に関する障害です。
例えば、しびれがあっても筋肉を動かせる場合がある一方、麻痺では動かしたくても、十分に動かすことができない場合があります。
両者を混同すると誤った対応につながります。
長く続くしびれを麻痺と誤解し、受診が遅れることは避けるべきです。
まとめると、しびれは原因や発生部位により大きく性質が異なります。
患者様やご家族様が正しく理解することが、適切なリハビリや生活改善につながります。
次の章では、このしびれが日常生活に与える具体的な影響について解説します。
しびれが日常生活に与える影響

この章では、しびれが患者様の生活にどのような影響を与えるのかを具体的に説明します。
動作や行動への制限だけでなく、ご家族様の介護負担、心理的ストレスや社会的孤立のリスク、さらには放置による二次障害について整理します。
患者様の動作・行動制限と転倒リスク
しびれがあると、歩行や立ち上がり動作が不安定になりやすくなります。
その結果、転倒の危険性が高まります。
特に高齢の患者様では転倒による骨折や寝たきりにつながる可能性があります。
- 階段や段差で足の感覚がつかみにくい
- 手先のしびれで食器を落とすことがある
- 歩行中に足の裏の感覚が鈍りつまずく
日常的なしびれは、生活の安全を脅かす要因になります。
ご家族様の介護負担と生活の変化
しびれにより患者様が動作に不安を感じると、ご家族様のサポートが必要になります。
食事や着替え、外出の付き添いが増えることで介護負担が大きくなり、生活リズムが変化することも少なくありません。
ご家族様自身の心身の疲労にもつながるため、適切な支援体制を整えることが大切です。
しびれによる心理的ストレスや社会的孤立
しびれは身体だけでなく心にも影響します。
患者様は「また転ぶかもしれない」と不安を抱え、外出や人との交流を控える傾向があります。
その結果、社会的な孤立や気分の落ち込みが生じやすくなります。
放置による二次的な障害(筋力低下や関節拘縮)
しびれを放置すると「動かしにくいから」と活動量が減り、筋力低下や関節の硬さ(拘縮)につながります。
これにより更なる動作制限が生じ、悪循環を招きます。
ただし、適切なリハビリを継続すれば進行を防ぎ、身体機能を保つことが可能です。
「治らないから仕方ない」と諦めることが、最大のリスクです。
まとめると、しびれは身体機能だけでなく心理面や社会生活、さらにはご家族様の生活にも影響を及ぼします。
正しい理解と早期対応により、生活の質を守ることができます。
次の章では、しびれ改善を目指す具体的なリハビリ方法を解説します。
しびれ改善を目指すリハビリ方法

この章では、しびれ改善に効果的とされる主なリハビリ方法を解説します。
運動療法や徒手療法、物理療法、日常生活動作訓練、自主訓練など幅広いアプローチを取り上げ、患者様やご家族様が自宅や施設で実践できる具体策を提示します。
運動療法(関節可動域訓練・筋力強化・ストレッチ)
運動療法は、しびれによって低下した筋力や柔軟性を回復させる基本的な方法です。
関節可動域訓練は固まった関節をほぐし、筋力強化は体幹や下肢を安定させる効果があります。
ストレッチは血流を促し、しびれを軽減する助けになります。
毎日の継続が神経回復を支える鍵となります。
徒手療法(ボバース・PNFなど専門家によるアプローチ)
徒手療法とは、理学療法士や作業療法士が手技を用いて行う治療法です。
ボバース法は神経の協調性を高め、PNF(固有受容性神経筋促通法)は動きを引き出すことを目的とします。
患者様一人ひとりの症状に合わせて選択されるため、安全性が高い点も特徴です。
物理療法(機能的電気刺激FES、TENS、温熱・冷却)
物理療法には、神経や筋肉に刺激を与えて症状を和らげる方法があります。
FES(機能的電気刺激)は筋肉の収縮を促し、TENS(経皮的電気神経刺激)は痛みやしびれを緩和します。
温熱療法は血流を改善し、冷却は炎症を抑える効果があります。
日常生活動作訓練(歩行、食事、着替えなどの練習)
日常生活動作訓練は、患者様が自立した生活を取り戻すために欠かせません。
歩行練習や階段昇降、食事動作や着替えといった基本的な動作を繰り返し練習することで、機能改善と共に自信を取り戻せます。
ご家族様の協力により継続がしやすくなります。
自主訓練・セルフケア(脱感作療法・自宅での工夫)
自主訓練では、タオルで皮膚をこする、さまざまな素材を触るなどの脱感作療法が有効です。
これは神経に多様な刺激を与え、感覚の再学習を促します。
自宅でできる運動やストレッチも取り入れれば、リハビリ効果を高めることが可能です。
ただし、無理をすると悪化の恐れがあるため、必ず専門職の指導を受けながら行いましょう。
まとめると、しびれ改善には複数のリハビリ方法を組み合わせることが重要です。
運動・徒手・物理療法、自主訓練をバランス良く取り入れることで、回復の可能性を最大化できます。
次の章では、最新のリハビリアプローチと自費リハビリ施設の取り組みについて解説します。
最新のリハビリアプローチと自費リハビリの役割

この章では、近年注目される最新のリハビリ技術やアプローチを紹介し、自費リハビリ施設での取り組みを解説します。
促通反復療法やCI療法、経頭蓋磁気刺激などの先進的な治療に加え、自費リハビリ施設だからこそ提供できる柔軟な支援や改善事例を紹介します。
促通反復療法やCI療法の効果と適応
促通反復療法は、神経のつながりを繰り返し刺激し、脳の可塑性を高める方法です。
繰り返し動作を行うことで運動学習を促進し、しびれの改善に寄与します。
CI療法(Constraint-Induced Movement Therapy)は健側の動きを制限し、麻痺側の使用を促す訓練です。
どちらも患者様の状態に応じて選択される先進的アプローチです。
経頭蓋磁気刺激(TMS)など先進的治療の可能性
経頭蓋磁気刺激(TMS)とは、頭部に磁気を当て脳の神経活動を活性化する方法です。
まだ研究段階ではありますが、しびれや麻痺の改善に効果が期待されています。
副作用が少なく非侵襲的である点が利点ですが、適応や効果の持続には個人差があるため、今後の研究成果が待たれています。
自費リハビリ施設における取り組みと改善事例
自費リハビリ施設では、保険制度の制限を受けず、時間をかけた集中的なリハビリを行えます。
例えば90分以上の個別訓練や最新機器を活用したプログラムを導入し、慢性的なしびれに悩む患者様が改善を実感した事例も報告されています。
「もっとリハビリを続けたい」という患者様のニーズに応えられる点が最大の強みです。
自宅リハビリと組み合わせるメリット・注意点
自費リハビリは、自宅での自主訓練と組み合わせることで効果が高まります。
専門職による指導を受けて正しい方法を学び、自宅で継続することが回復の近道です。
ただし、誤った方法で行うと症状が悪化する可能性があるため、必ず定期的に専門職に相談することが重要です。
「自己流」だけに頼ることはリスクがあるため、専門的な支援との併用が欠かせません。
まとめると、最新のリハビリ技術と自費リハビリ施設の柔軟なサポートを組み合わせることで、しびれ改善の可能性は広がります。
次の章では、改善が難しい場合に役立つ生活の工夫や、ご家族様による支援の方法について解説します。
自費リハを選んだ患者様の事例
脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。
【出生時発症】10代男性・脳性麻痺の改善事例 – 脳卒中・脳梗塞・脳出血の後遺症改善
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【出生時発症】10代男性・脳性麻痺の改善事例 – 脳卒中・脳梗塞・脳出血の後遺症改善
実際に自費リハを利用された患者様からは、継続する意義を実感する声が多く寄せられています。
「もう少し頑張りたい」「もっと回復したい」──という声に寄り添えるのが自費リハビリです。
↓↓↓自費リハビリ選びにお困りの方は、是非こちらの記事をご覧下さい。
【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!
しびれと向き合うための工夫と今後の選択肢

この章では、しびれが完全に改善しにくい場合でも生活の質を守るための工夫を解説します。
ご家族様のサポート方法や、福祉用具・生活環境の調整、受診や相談の目安を整理し、今後の選択肢を広げるための視点を提示します。
改善が難しい場合に取り入れる生活の工夫
しびれが残っても生活の工夫次第で快適さは向上します。
例えば、歩行時に転倒を防ぐためには滑りにくい靴や手すりの設置が有効です。
食事動作では軽量の食器を用いることで負担を減らせます。
完治を目指すだけでなく「慣れる工夫」を取り入れることも大切です。
ご家族様ができる具体的なサポート方法
ご家族様の支援は患者様の生活を大きく支えます。
外出時の付き添いや、リハビリを継続しやすいよう声かけを行うことが効果的です。
また、心理的に寄り添うことで「一人ではない」という安心感を与えられます。
サポートの過剰負担を避けるため、介護サービスや地域の支援も活用することが望ましいです。
福祉用具や生活環境調整でQOLを高める方法
福祉用具を取り入れることは、安全性と自立を高める手段になります。
杖や歩行器は転倒予防に役立ち、滑り止めマットや段差解消グッズは家庭内での事故を減らします。
- 転倒防止のための杖や歩行器
- 段差をなくすスロープや手すり
- しびれで物を落としやすい方には滑り止め付き食器
ご家族様と一緒に生活環境を整えることで、患者様が安心して生活を続けられます。
受診や相談の目安|何日続いたら医師に相談すべきか
しびれは数分で改善する一過性の場合もありますが、数日以上続く場合は注意が必要です。
特に、片側だけに出現するしびれや急に悪化する症状は脳卒中の可能性があるため、速やかに医師へ相談してください。
「様子を見すぎる」ことが重症化のリスクを高めます。
まとめると、しびれに向き合うには改善を目指すリハビリに加えて、生活環境の調整やご家族様の支援が欠かせません。
医療機関への早期相談も含め、複数の選択肢を活用することで、患者様の生活の質を守ることが可能です。
次の章では、これまでの内容を整理しまとめとして解説します。
まとめ

この記事では、しびれの原因や特徴、日常生活への影響、改善を目指すリハビリ方法、最新アプローチ、自費リハビリの役割、さらに生活上の工夫やご家族様のサポートまで幅広く解説しました。
しびれは何もしなければ悪化する恐れがありますが、適切な対応で生活の質を維持・改善することができます。
- しびれは中枢性・末梢性で原因が異なる
- 日常生活への影響は身体・心理・社会面に及ぶ
- リハビリは運動療法・徒手療法・物理療法・日常生活動作・自主訓練を組み合わせる
- 自費リハビリ施設や先進医療で選択肢が広がる
- 生活環境の工夫とご家族様の支援が安心につながる
早めの受診と継続的なリハビリは、改善の第一歩です。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・横浜八景島シーパラダイスや山下公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

中田 裕
理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中 / 管理・運営)
2003年に理学療法士免許を取得。回復期、維持期、外来、デイケア、地域支援事業でのリハビリを経験。小児から老年期に至るまで幅広くリハビリに携わり、中でも脳血管疾患や神経難病の患者のサポートを精力的に実施。2013年にボバース認定基礎講習会を修了、2015年には認定理学療法士(脳卒中)及びNST専門療法士を取得。2024年11月より脳神経リハビリセンターに勤務。
私は「利用者様の想いをかたちにするリハビリ」を大切にしています。運動のプロフェッショナルとして根拠に基づき、利用者様とともに最善の結果に到達できるよう努力していきたいと思います。皆様との出会いを楽しみにしております。





