お知らせ
NEWS
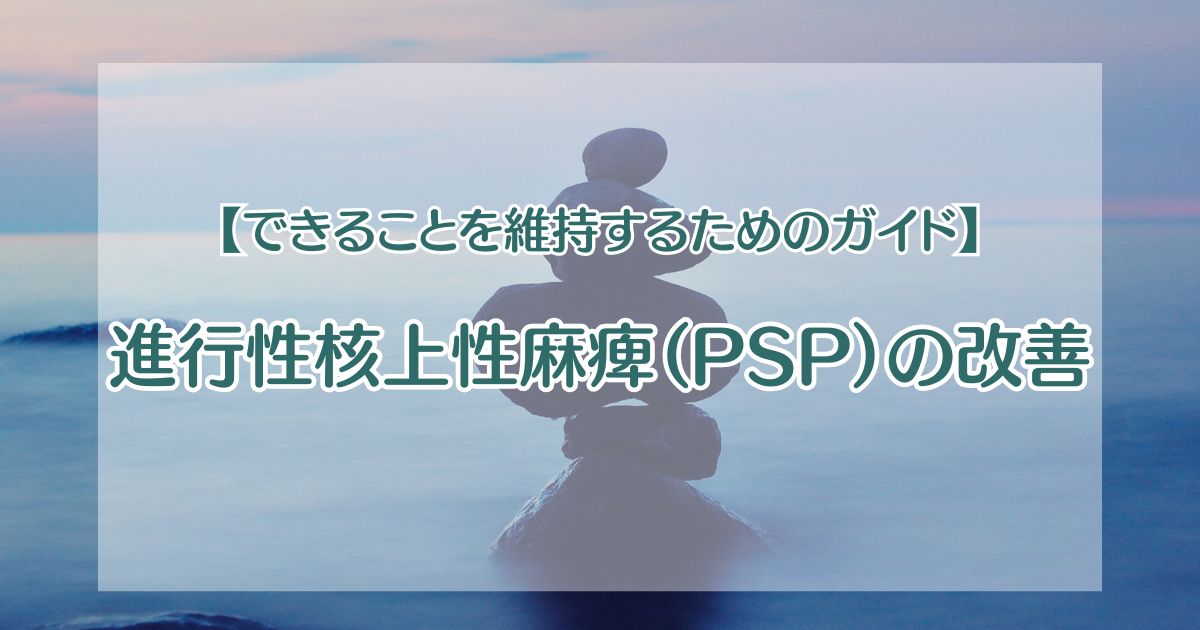

進行性核上性麻痺と診断され、「改善の見込みはあるのか」と悩む方は少なくありません。
ご本人様やご家族様が不安を感じられている中であっても、何もせずに過ごすことは、身体機能の低下や生活の質(QOL)の低下につながるリスクがあります。
状況に応じて、無理のない範囲での活動を継続していくことが大切です。
この記事では、リハビリ専門職の視点から、できることを「維持・増やす」ための具体策をご紹介します。
希望をもって日常に向き合う一歩を踏み出していただければ幸いです。
1. 進行性核上性麻痺(PSP)を理解する|リハビリの目的を見失わないために

この章では、進行性核上性麻痺(PSP)の特徴や運動障害の原因、日常生活に表れやすい初期症状、ご本人様やご家族様が抱える心理的な不安について説明します。
病気の理解を深めることで、リハビリの目的を見失わず、前向きに生活を整えていくヒントが得られます。
1-1. PSPの概要|運動やバランスの障害が起きる理由
PSPとは、主に中高年に発症する神経の働きが徐々に弱くなる病気です。
脳の深部にある「大脳基底核」や「脳幹」といった運動の調整を行う部分の機能が低下することで、姿勢保持や目の動き、歩行の安定性が損なわれます。
身体機能が徐々に衰えていく病気であることから、介助やリハビリを早期に取り入れることが非常に重要です。
特に、リハビリを行ううえで押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
- 運動の指令が出ても、身体が滑らかに動きづらくなる
- 後ろに倒れやすくなる「後方転倒」が特徴的
- 視線を上下に動かしづらくなり、転倒リスクが増す
筋肉の力が弱っているわけではなく、動きを調整する脳の機能低下が原因である点に注意が必要です。
力任せの訓練ではなく、姿勢や視線の補助を含む安全なアプローチが求められます。
1-2. 初期症状でよく見られる歩行の変化や転倒のリスク
PSPの初期には歩き方や立ち座りに微妙な変化が現れます。
ご本人様も気づかないことが多く、ご家族様が先に異変を感じるケースも少なくありません。
この段階での気づきが、リハビリや安全対策の早期介入につながります。
具体的には以下のような兆候が見られます。
- 足が前に出づらく、すり足になる
- 歩いている最中にバランスを崩して後ろに倒れる
- 下を見る動作が苦手になり、段差に気づきにくい
これらの変化は、単なる「老化」や「運動不足」と見逃されやすいです。
ですが、転倒が骨折や入院につながるリスクを高めるため、リハビリによる早期対応が重要です。
1-3. ご本人やご家族様が抱きやすい不安とその背景
PSPと診断された直後は、ご本人様もご家族様も大きな不安に包まれます。
特に「改善しないのではないか」「将来寝たきりになるのでは」といった漠然とした心配が強くなりやすいです。
このような不安に向き合いながら、前向きに日常生活を整えていくことが求められます。
そこで大切なのは、「できること」に目を向けて支える視点です。
完璧なサポートを目指すのではなく、リハビリを通じて生活の質を維持する工夫が、安心につながります。
2.「改善」とは何か|できることを増やす・維持するという考え方

この章では、進行性核上性麻痺(PSP)における「改善」という言葉の捉え方を整理し、実際に目指すべき現実的な目標や、ご本人様の意欲を引き出す視点、小さな変化に注目する重要性について解説します。
機能の維持や生活の質の向上を目指すことで、リハビリの効果を最大限に引き出す考え方を身につけられます。
2-1. リハビリの目標は「機能の回復」より「できる動作の維持と安全性」
PSPにおけるリハビリは、完全な回復を目指すものではありません。
大切なのは、進行のスピードを緩やかにしながら、「今できること」を少しでも長く維持し続けることです。
そのためには、身体機能を守る工夫と、日常生活の中での実用的な動作をリハビリに組み込むことが重要です。
- 無理な訓練よりも、安全に継続できる内容を優先する
- 歩行・起居・排泄といった生活動作を中心に組み立てる
- 「今できる動き」を維持すること自体が改善と捉える
焦って結果を求めすぎると、心身の負担が増えかえって逆効果になることもあります。
リハビリの方向性は、専門職と相談しながら無理なく見直していくことが大切です。
2-2. ご本人のやる気や生活習慣も改善の一歩になる
リハビリの効果を高めるには、ご本人様自身の気持ちや取り組む姿勢が欠かせません。
毎日の生活リズムを整えたり、運動を日課にすることが、小さな改善につながります。
「できないこと」ではなく、「やってみようと思えること」に意識を向けて取り組むことがポイントです。
たとえば以下のような工夫が効果的です。
- 朝決まった時間に起きて、日中の活動量を増やす
- 座ってできる運動や体操を毎日10分続けてみる
- ご家族様と一緒に食卓を囲む時間を習慣化する
これらは専門的な訓練でなくても、生活の中に自然とリハビリを取り入れる方法として有効です。
2-3. 小さな変化に気づくことが、モチベーションにつながる
PSPでは、目に見える大きな改善は少ないかもしれません。
しかし、「昨日より転ばなかった」「表情が和らいだ」などの小さな変化に気づけることが、ご本人様やご家族様の励みになります。
こうした変化を記録したり共有することが、リハビリを継続する力になります。
セラピストが日々の変化を見つけて伝えることも、モチベーション維持に役立ちます。
「続ける価値がある」と感じられるリハビリ環境を整えることが、長期的な支えとなります。
3. 改善に向けたリハビリの実際|理学療法士・作業療法士のサポート内容

この章では、進行性核上性麻痺(PSP)の患者様に対して、理学療法士や作業療法士がどのような支援を行うのかを紹介します。
身体機能の維持と日常生活の安定を目的とし、症状に合わせて行うリハビリ内容について具体的に解説します。
3-1. 姿勢とバランスを整える訓練(転倒予防・移動動作)
PSPでは、姿勢の保持が難しくなり、後方への転倒リスクが特に高くなります。
理学療法士は、立位の安定性や歩行時の重心コントロールを高める訓練を行い、安全な移動を支援します。
- 重心の左右移動や膝の屈伸などの基本動作訓練
- 立ち上がりや方向転換時の姿勢制御訓練
- 歩行器や手すりを活用した安全な移動訓練
転倒を防ぐ環境調整も重要であり、ご自宅での動線や段差への配慮も支援対象です。
3-2. 関節のこわばりを防ぐストレッチや柔軟体操
運動量の低下によって関節が硬くなると、動作の範囲が狭まり、転倒や痛みの原因になります。
理学療法士や作業療法士は、柔軟性を保つためのストレッチや可動域訓練を継続的に実施します。
たとえば以下のような取り組みがあります。
- 肩・股関節など大関節の可動域を保つ静的ストレッチ
- 背中や首の緊張を和らげる上半身のストレッチ
- 座位でできる下肢の筋伸張体操
無理に力を入れると筋緊張が高まるため、反動をつけない穏やかな動作が推奨されます。
3-3. 日常生活動作(食事・更衣・トイレなど)の練習
PSPが進行すると、日常生活動作の一部が難しくなることがあります。
作業療法士は、食事・着替え・排泄などの「生活に直結する動作」の練習を支援します。
訓練は、動作の順序を整理し、安全かつ自立して行える方法を一緒に探る形で進められます。
改善が難しい動作に対しては、補助具の活用や代替手段の提案を行います。
3-4. リハビリを継続しやすくする工夫(時間・頻度・関わり方)
効果的なリハビリを続けるためには、内容だけでなく「続けやすさ」も重視する必要があります。
時間や頻度、ご本人様の調子に合わせた柔軟な調整が、モチベーション維持につながります。
セラピストは、以下のような視点でリハビリを設計します。
- 1回あたりの時間を短めにし、集中しやすい構成にする
- 「今日は何をやったか」を振り返る声かけを取り入れる
- ご家族様にも関わってもらい、見守りや声かけを習慣化する
その日の調子を見極めながら「頑張りすぎず、やめずに続ける」ことが、リハビリ成功の鍵です。
4. ご家族様ができる支援と、生活環境を整えるためのポイント

この章では、進行性核上性麻痺(PSP)の患者様を支えるご家族様に向けて、日常生活で実践できる支援の工夫や、転倒予防に役立つ住環境の整備、介助の際に気をつけたいポイントについて紹介します。
無理のない介助と安全な環境が、ご本人様の意欲と安心を支える鍵となります。
4-1. 転倒リスクを減らす家具配置や福祉用具の活用
PSPでは後方への転倒が多く、室内でも事故が起こるリスクがあります。
そのため、ご自宅の家具配置や通路の確保に工夫を加えることで、転倒を未然に防ぐ環境づくりが重要となります。
たとえば以下のような対策が効果的です。
- 家具を壁際に寄せ、歩行ルートを広く取る
- ラグや電気コードなど、つまずきやすい物を除去する
- 手すりや歩行補助具を必要な場所に設置する
動線が狭い・暗い・滑りやすいといった要因は、転倒を誘発します。
照明や床材も含めて、安全性の高い空間づくりを心がけましょう。
4-2. 食事や入浴の動作をスムーズにする介助の工夫
日常生活では、食事・更衣・入浴などの動作が難しくなってきます。
ご家族様の介助が必要な場面では、「手伝いすぎない」ことも大切です。
ご本人様の残存能力を尊重し、できる範囲で一緒に行うことが自立心の維持につながります。
介助時の注意点としては以下が挙げられます。
- 食事は一口の量や姿勢に注意し、むせを防ぐ
- 入浴時は浴槽のまたぎや滑りに特に注意する
- 着替えは座位保持を安定させたうえで行う。
いずれの動作においても声かけを行いながら「手を出す前に、声をかける」ことが、信頼と安心感につながります。
「手を出す前に、声をかける」ことが、信頼と安心感につながります。
4-3. ご家族様自身の負担を減らすための視点と相談先
介護は長期戦です。
ご家族様が疲弊してしまうと、ご本人様への支援も難しくなります。
そのため、「ご家族様自身のケア」も非常に大切です。
頼れる相談先や支援制度の活用が、日々の負担を軽減する手段になります。
- 地域包括支援センターで介護相談や制度案内を受ける
- ケアマネジャーに福祉用具や訪問サービスの相談をする
- デイサービスやショートステイを定期的に利用する
「ひとりで抱え込まない」ことが、長く支え続けるための第一歩です。
5. より良い生活のために活用できる支援制度やサービス

この章では、進行性核上性麻痺(PSP)の患者様とご家族様が、安心して生活を続けるために活用できる支援制度やサービスについて解説します。
制度を正しく理解し、適切な支援を受けることは、身体的・精神的な負担軽減に大きくつながります。
5-1. 通所リハビリ・訪問リハビリ・自費リハビリの違いと活用法
リハビリサービスには複数の形態があり、それぞれ特徴と利用条件が異なります。
目的や生活スタイルに応じて適切なサービスを選ぶことが、継続的な支援につながります。
- 通所リハビリ:施設に通い、定期的に専門職の支援を受ける(対人交流が必要な方に有効)
- 訪問リハビリ:自宅でリハビリを受ける(外出困難な方に有効)
- 自費リハビリ:保険外で専門的な個別支援を受けられる自由度の高いサービス(よりリハビリによる改善を希望される方に有効)
「継続できる形」で選ぶことが最も重要であり、リハビリの効果を左右する要素となります。
5-2. 継続的なリハビリを支えるスケジュールと相談体制
リハビリの効果を高めるには、継続できる仕組みづくりが大切です。
そのためには、ご本人様の体調や生活リズムに合わせた柔軟なスケジュール調整と、相談しやすい体制の構築が必要です。
以下のような体制づくりが、リハビリの継続を後押しします。
- 体調に応じて週1~2回からスタートし、無理のない頻度に調整
- リハビリの記録を残し、ご家族様とも共有
- 疑問や困りごとをすぐ相談できる窓口を確保
「継続しやすい環境」を整えることが、生活の安定と自信の積み重ねにつながります。
5-3. 自費リハビリ施設を利用するメリットと注意点
自費リハビリでは、医療保険や介護保険の枠にとらわれず、集中的なリハビリを行うことが可能です。
- 保険制度外でも、リハビリ時間や頻度を柔軟に設定できる
- 専門職によるマンツーマン指導が受けられる
- 機能改善を目的とした集中プログラムが組まれる
費用は全額自己負担です。継続できる計画と目的を明確に持つことが大切です。
脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。
仮に進行性の疾患であると診断がついた場合でも、専門職が介入し適切なリハビリを行うことで日常生活は大きく変わります。
希望をもって一歩を踏み出していただくため、実際にリハビリを行った方の事例を紹介いたします。
【発症後10年】60代女性・パーキンソン病の改善事例
朝起床時の起き上がりが30分程かかるとのことで、パーキンソン病に特化したリハビリが実施したいと希望あり、来店して頂きました。
起き上がり動作や座位姿勢に改善を認めました。
ご自宅での起き上がりは時間をかけずに円滑に行えるようになり、動作時の腰痛も生じなくなりました。
座位姿勢は、初期は右肩が下がり、頚部も右に傾いている姿勢でしたが、現在は肩・頚部ともに傾きが少なくなり真っ直ぐな姿勢がとれるようになりました。
左右対称な姿勢がとれることで、身体を固めずに手足を大きく動かしながら歩行を行うことができるようになりました。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【発症後10年】60代女性・パーキンソン病の改善事例
【発症後4年】60代女性・パーキンソン病の改善事例
発症後、徐々に介助を要するようになり約2年前から症状が急激に悪化し、生活全般に全介助を要する状態でした。
HPで当施設をご覧いただき、ご利用頂くことになりました。
歩行の介助量で改善を認めました。
初期は療法士が後方からしっかり支えて、5mが何とか歩ける状態でした。
現在は歩行器を使用して、見守りで連20m程の歩行が可能になっております。
歩行時の体幹の姿勢も改善してきております。
初期に著明に認めていたパーキンソンの症状で認めやすい突進歩行(前のめりになってしまう歩行)も改善を認めます。
↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。
【発症後4年】60代女性・パーキンソン病の改善事例
↓↓↓自費リハビリの選び方については、こちらの記事をご参照ください。
【料金・頻度・施設選定まで解説!】失敗しない自費リハビリの選び方
6. まとめ

本記事では、進行性核上性麻痺(PSP)における症状の理解から、リハビリの考え方、日常生活における支援の工夫、活用できる制度やサービスまでを幅広く解説いたしました。
進行性核上性麻痺(PSP)においては「改善」という言葉のみにとらわれず、「できることを維持し、生活の質を守る」ための工夫やサポートについて考えることが大切です。
要点を整理すると以下の通りになります。
- PSPの運動障害にはリハビリによる早期対応が有効である
- 機能回復ではなく「できる動作の維持・改善」がリハビリの目的と考える
- 日常動作や安全な移動を中心とした実践的サポートを行うことで転倒は防げる
- ご家族様の支援は、無理なく継続できることを前提に行う
- 公的なサービスを利用することでご家族様の負担を減らすことができる(通所リハビリ、訪問リハビリ)
- 専門的で自由度の高い自費でのリハビリサービスを活用することで症状の改善が期待できる
今の暮らしを少しでも長く、安心して続けるために、リハビリと支援の選択肢を知り、行動に移すことが未来への備えになります。
患者様とご家族様が共に支え合い、前を向けるよう、私たちリハビリ専門職も伴走いたします。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
↓お問い合わせはこちらから
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>神奈川にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)
>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)
>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)
Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
この記事を書いた人

細葉 隆
理学療法士
2006年に理学療法士免許を取得。
一般病院・訪問リハビリ・介護老人保健施設・通所リハビリと全てのステージで脳卒中を中心としたリハビリを経験。
2024年、公的保険で回復できなかったお客様の改善をしたいという想いから、脳神経リハビリセンター仙台に勤務。
私はこれまでに様々なお客様とそのご家族とリハビリを通して関わってきました。お客様の夢や目標に向かってチームとして、そしてセラピストとして携わってきました。私のモットーはお客様や家族の方と同じ方向を向き、寄り添いながら一緒に進んでいくことです。
脳神経リハビリセンターでは、充分な時間と最新の機材が整っており、リハビリを必要としている方の夢を叶える場所であると確信しています。
1回1回のリハビリを通じて、小さな変化や気付きに喜びを分かち合い、目標が達成に向けて一緒に頑張ってみませんか。
皆様との出会いを楽しみにしています。





