お知らせ
NEWS
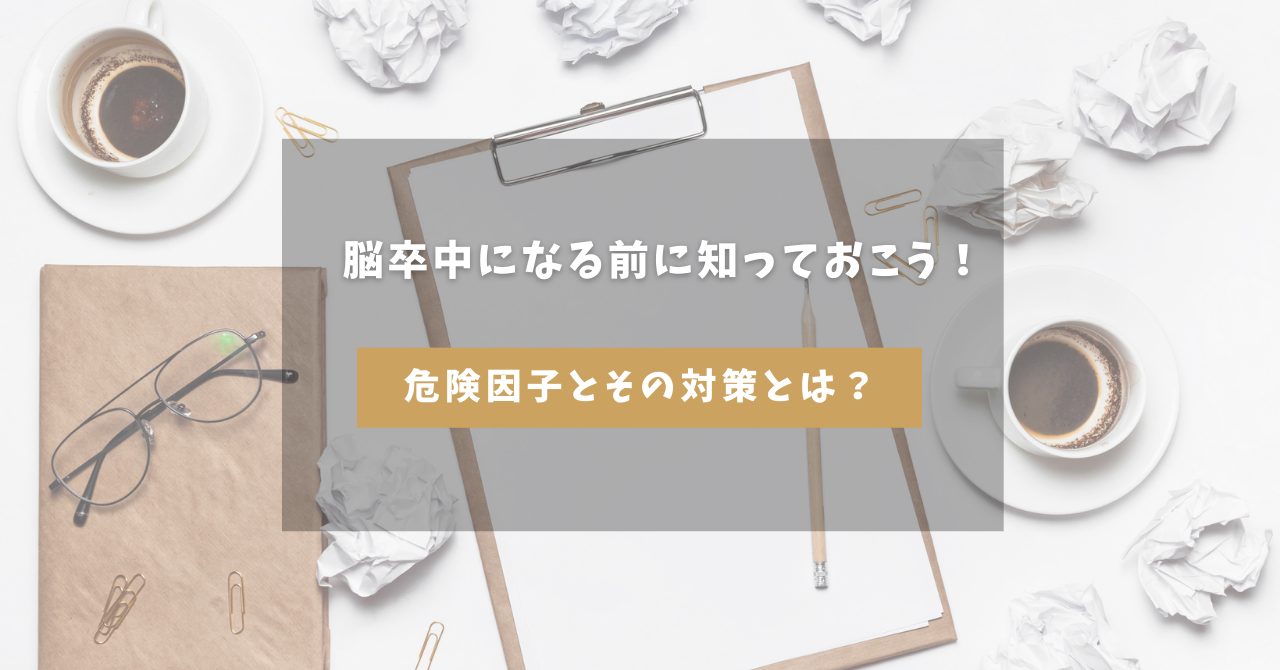

近年、40-60歳の現役世代で脳卒中になる方が増えています。
脳卒中になりやすい人はどんな危険因子を持つ人なのでしょうか。
この記事では、脳卒中になりやすい危険因子と、その理由、罹患と再発のリスクを減らす対策をご紹介します!
今のうちから自分のリスクを見直して、脳卒中にならない・再発しないための対策をしっかりしていきましょう!
心当たりはありますか? 脳卒中の原因となる生活習慣
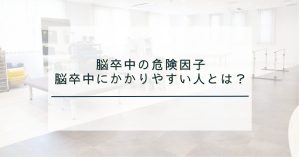
脳卒中のリスクを知っていますか?
40歳をすぎると脳卒中にかかるリスクが急上昇すると言われています。
では具体的にどんな人が脳卒中にかかりやすいのか、脳卒中の危険因子について解説していきます!
脳卒中になりやすい人
以下の要因が複数あることで、脳卒中のリスクが高まります。
・喫煙者
・肥満の人
・高血圧の人
・糖尿病の人
・心臓病の人
・運動不足の人
・生活習慣病の人
・高コレステロールの人
・過度にストレスを感じている人
これらの危険因子は、予防と早期発見が重要とされています。
ストレスと脳卒中の予防方法についてはこちらでくわしく解説しています!
5大危険因子
脳卒中においてもっとも重要な危険因子は、以下の5つです。
1.高血圧
2.心房細動
3.糖尿病
4.高コレステロール
5.喫煙
これらの危険因子を持つ人は、脳卒中にかかるリスクが高くなります。
5つの危険因子のなかでも、高血圧は脳卒中の最大のリスク因子とされています。
高血圧は動脈硬化をすすめ、動脈が破裂するなどして脳出血をひきおこすことがあります。
また、高血圧がつづくと、脳梗塞のリスクも高まります。
自分のリスクをチェックしよう

自分が脳卒中にかかるリスクを知ることは、予防のためにとても重要です。
以下のような方法でセルフチェックを行うことができます。
喫煙
運動をしていない
高血圧の既往がある
糖尿病の既往がある
BMIが高い(25以上)
ストレスを抱えている
家族に脳卒中や心臓病の人がいる
脳卒中の予防方法
脳卒中の予防方法について紹介します。脳卒中の予防には、以下のような方法があります。
1.生活習慣の改善
禁煙、適度な運動、バランスの良い食事、アルコールの適量摂取など、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。




2.血圧・血糖・コレステロールの管理
定期的な健康診断や医師の診断を受け、血圧・血糖・コレステロールなどを管理することが重要です。
3.脳ドックの受診
脳ドックは、脳卒中のリスク評価や早期発見のために有効な検査です。
知ってますか?脳卒中の症状と原因
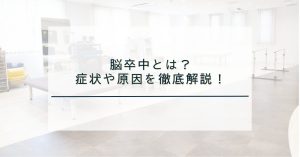
脳卒中は、一度発症すると大きな後遺症がのこる場合があり、命にもかかわる危険な病気です。
今回は、脳卒中の原因や予防方法、早期発見のための情報を徹底解説します!
脳卒中の症状
脳卒中の症状は、以下のようなものが挙げられます。
・感覚障害:片側や顔などの感覚が鈍くなる、しびれる
・視野障害:片側の目が見えなくなる、二重視する
・言語障害:話すことができなくなる、言葉がうまく出なくなる
・>その他:急激な頭痛、めまい、嘔吐、意識障害など
これらの症状が現れた場合は、すぐに病院へ行くことが大切です。
脳卒中の原因

脳卒中の原因は以下の要素が大きく関わってきます。
生活習慣病
・糖尿病
・脂質異常症
生活習慣
・運動不足
・過度の飲酒
その他
・年齢
・ストレス
虚血性脳卒中の場合は、動脈硬化が進行し、血管内に血栓やプラークができることが原因になります。
出血性脳卒中の場合は、血管壊死(血管が壊れて出血)が原因となります。
脳卒中の種類
脳卒中には大きく分けて以下の3つがあります。
脳出血:脳内の血管が破れて出血することで脳がダメージを受ける病気
脳梗塞:脳内の血管が詰まることでその際の脳細胞が壊死する病気
くも膜下出血:血管が破れくも膜下腔に血液が流れることで意識障害などをきたす病気
くも膜下出血に関して詳しくはこちらの記事もご覧ください!
脳卒中の予防方法
脳卒中を予防するためには、生活習慣の改善が重要です。
また、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病がある場合は、適切な治療を受けることが必要です。
さらに、ストレスや睡眠不足に注意し、適度な休息を取ることも大切です。
脳卒中の早期発見のために
脳卒中は、早期発見が重要です。
脳卒中の兆候としては、急に頭痛がしたり、手足のしびれや動かしにくさ、言葉の不明瞭さなどが挙げられます。
これらの症状がおこったら、すぐに救急車をよびましょう。
脳卒中の治療は時間とのたたかいであり、早期治療が生死をわけることもあります。
脳卒中を早くみつけるためのポイントで『FAST』というものがあります。
↓↓↓くわしくはコチラをご覧下さい!
脳梗塞と麻痺について
気をつけて!脳卒中につながりやすい病気4選
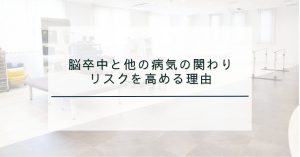
糖尿病
糖尿病の患者さんは、高血糖が原因で血管がきずつくことがあります。
そのため、糖尿病の患者さんは、脳卒中をひきおこすリスクが高まることがしられています。
また、糖尿病の合併症である高血圧、高コレステロール血症も脳卒中のリスク要因となります。
高血圧
高血圧の患者さんは、脳卒中をひきおこすリスクが高まります。
高血圧は、そして、脳卒中の原因のひとつである脳出血につながる可能性があります。
脳出血とは、脳内の血管が破裂することにより、脳内に出血がおこる病気です。
また、高血圧は、動脈硬化を進行させることもあります。
動脈硬化
動脈硬化は、高血圧や高コレステロール血症、喫煙などの要因によって生じることが多いです。
生活習慣の改善が予防につながります。
心臓病
心臓病は、脳卒中のリスクをふやす要因のひとつです。
心臓病の患者さんは、心臓が正常にはたらかないため、血液中の酸素不足が起こります。
この酸素不足により、脳卒中をひきおこすリスクが高まります。
脳卒中にならないためには?危険因子を減らす方法3選
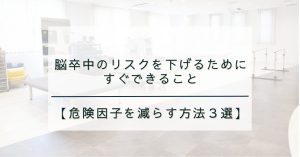
脳卒中は、一度発症すると後遺症がのこり、生活に大きな影響をあたえる恐れがあります。
そこで脳卒中を予防するために、自分自身でできる対策が求められます。
ここでは、脳卒中のリスクをさげるために、すぐに実践できる予防方法を3つ紹介します!
1.血圧のコントロール
まずは血圧を正常範囲でコントロールすることです。
高血圧は、脳卒中のリスクを高める最も大きな危険因子です。
高血圧は、血管を収縮させ、血管内の血液を流れにくくします。
そのため、血圧が高い状態が続くと、脳卒中や心筋梗塞のリスクが上がってしまいます。
血圧を下げるためには、生活習慣の改善が効果的です。
まずは、塩分の摂取量をひかえめにすることが大切です。
また、タバコを控えたり、適度な運動を行ったりすることで、血圧を下げることができます。
2.生活習慣の見直し
脳卒中のリスクを下げるためには、生活習慣の見直しも大切です。
不規則な食生活や過剰なアルコール摂取、睡眠不足などは、脳卒中のリスクを高める要因となります。
健康的な食生活を心がけ、アルコールやタバコの過剰摂取をさけ、十分な睡眠をとるようにしましょう。
また、ストレスも脳卒中のリスクを高める要因の一つです。
ストレスを感じたときには、適切なリラックス法を見つけることが大切です。
生活習慣病の予防に関してくわしくはこちらの記事もお読みください!
3.脳ドック
リスクにはやく気づくためにおすすめな方法が脳ドックです。
脳ドックは、MRIやCTなどの検査を行うことで、脳に異常がないかを確認することができます。
脳卒中のリスクを下げるためには、定期的に脳ドックを受けることが大切です。
特に、高血圧や糖尿病などの脳卒中の危険因子がある人は、定期的な脳ドックを受けましょう。
なぜなら早期発見につながり、適切な治療が受けられる可能性が高くなるからです。
脳ドックを受けることで、脳卒中のリスクを下げるためのアドバイスや、必要な治療方法を知ることもできます。
また、脳に異常がないことが確認されれば、安心感が得られることもメリットの一つです。




早期にリスクを知るにはとても有効な方法です。
脳卒中の患者様からよくある悩み相談とその解決策


脳卒中後の適切な対応を行うことにより、患者様の予後や回復が大きく変わります。
この章では、患者様とご家族様が実際に直面した問題と、それに対する具体的な解決策についてご紹介します。
脳卒中後のリハビリテーションについて
脳卒中後のリハビリテーションは、早期から始めることが重要です。
- 個々の症状に合わせた適切なプログラムを受ける
やみくもに回数だけをこなしても成果にはつながりません。
専門家の指導の下リハビリを行いましょう。
- 日常生活に役立つ基本動作の練習を行う
日常生活でできることが増えるとモチベーションが上がり自信にも繋がります。
- 心理的なサポートを受ける
脳卒中を発症してすぐのリハビリは辛いものです。
悩みを相談しながら行うことが大事です。
日常生活への適応方法について
脳卒中の患者様が自宅に帰った後、安全に生活するための対策をご紹介します。
- 住環境のバリアフリー化を進める
- 必要な福祉用具を利用する
入院期間中に完全に元の身体機能を取り戻すことが難しい場合が多いです。
その方の身体の状態に併せて過ごしやすい環境を整えることが大事です。
- 家族や介護者のための研修を受ける
脳卒中後、一人で在宅生活を行うのは困難な場合が多いです。
サポートに関わる家族様の介護負担や、悩みに対してのフォローも重要です。
再発防止のための注意点について
脳卒中の再発を防ぐためには、以下の点に注意が必要です。
- 定期的な健康診断と症状の確認を行う
自覚症状の有無にかかわらず医師の診察を受け、体の状態を知ることが大事です。
- 食生活や運動習慣の改善を図る
バランスの悪い食事や運動不足は脳卒中の再発に繋がる可能性があります。
日ごろから気をくばるようにしましょう。
在宅生活における精神的なサポートとケア
脳卒中患者様やご家族様の心の健康も、リハビリに大きく影響します。
心理的な問題を解決するためには以下のような方法があります。
- 専門のカウンセラーによるサポートを受ける
- 社会とのつながりを保つための活動を積極的に行なう
ご家族様へのアドバイス
ご家族様が適切なサポートを行うためのポイントは以下のようなものがあります。
- 本人様の状態を理解し、適切な対応方法を知る
- 専門家のアドバイスを聞く
- ご自身の休息時間も大切にする
お客様からいただいた困りごとと、セラピストからのアドバイス
実際にお客様からいただいた困りごとの一例をご紹介します。
お客様からいただいた困りごと
毎朝の支度が大変で、特に着替えや靴を履くのに時間がかかり、日常生活に影響が出ている。
セラピストからのアドバイス
一口に着替えや靴の脱ぎ履きが行いづらいといっても様々な原因があります。
まずはどのように大変かを評価していくことが大事です。
- 関節が硬くなって動きにくい
- 筋力が弱くて動かしにくい(できない)
- 麻痺によって目的とした動作を行うことが出来ない・・・等
原因を特定し、それぞれの原因に合ったリハビリを行うことが重要です。
例えば、麻痺が原因で目的とした動作を行うことが出来ない場合を考えます。
この場合、麻痺した手足を動かす練習を行った上で、実際の動作の練習を適切な環境で実施することで、体が効率の良い動きを覚え動作の獲得に繋がることがあります。
自助具という困っている動作を手助けしてくれる道具(靴ベラなど)を使用することも方法の一つです。
また、服のサイズを大きくするなど体の状態に合わせて工夫(環境調整)することも大事です。
まとめ
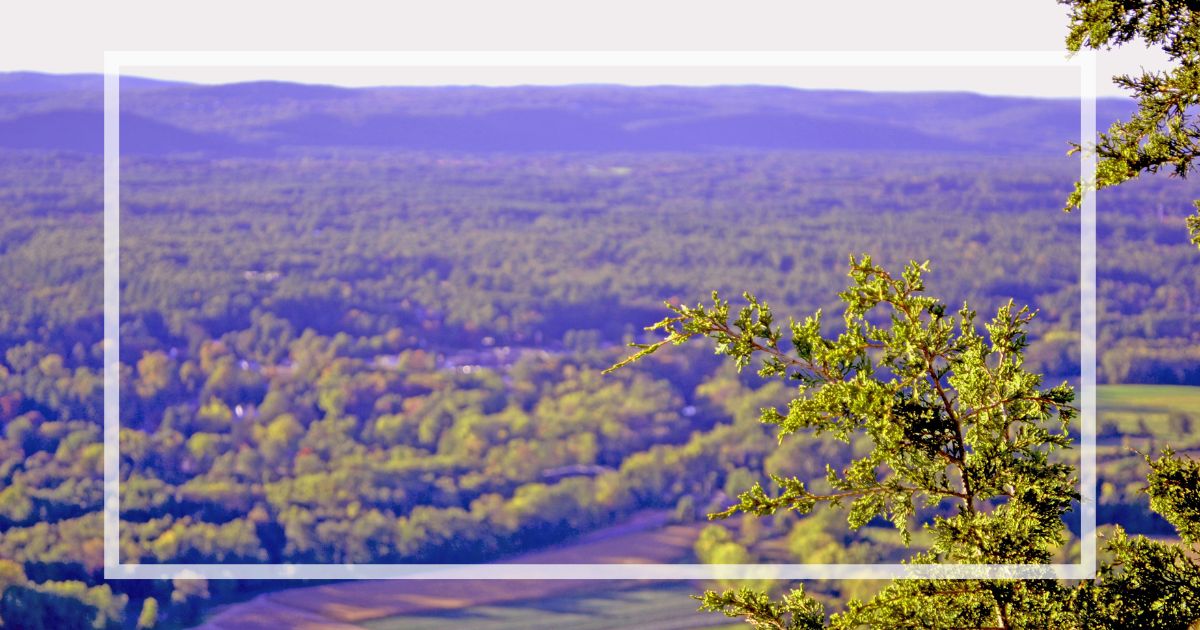
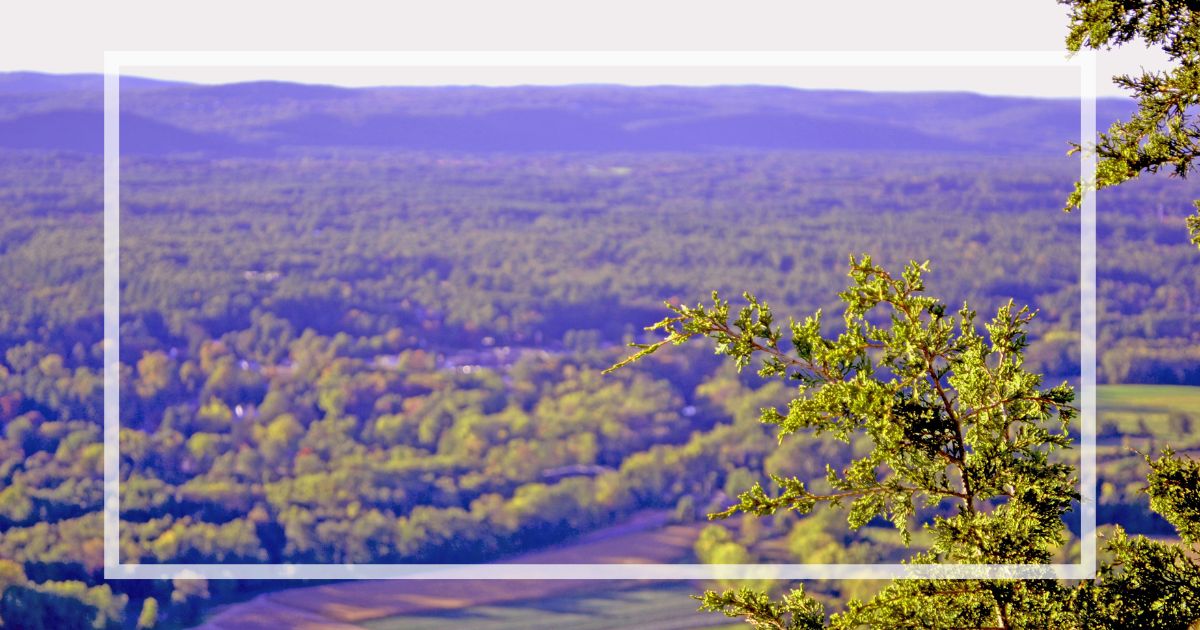
いかがでしたか?
ここまで、脳卒中のリスク要因と対策について詳しくご説明してきました。
脳卒中の主なリスク要因としては、高血圧、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足があります。
定期的な運動や健康的な食生活、禁煙、定期的な健康チェックなどが効果的な予防策とされています。
脳卒中は、予防することができます。
生活習慣の改善や定期的な運動などできることから始めていきましょう。
本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください


弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。
・維持ではなく、改善をしたい
・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい
このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。
毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!
お問い合わせはこちらから↓
>>仙台付近にお住いの方
>>東京にお住いの方
>>名古屋付近にお住いの方
>>大阪付近にお住いの方
この記事を書いた人
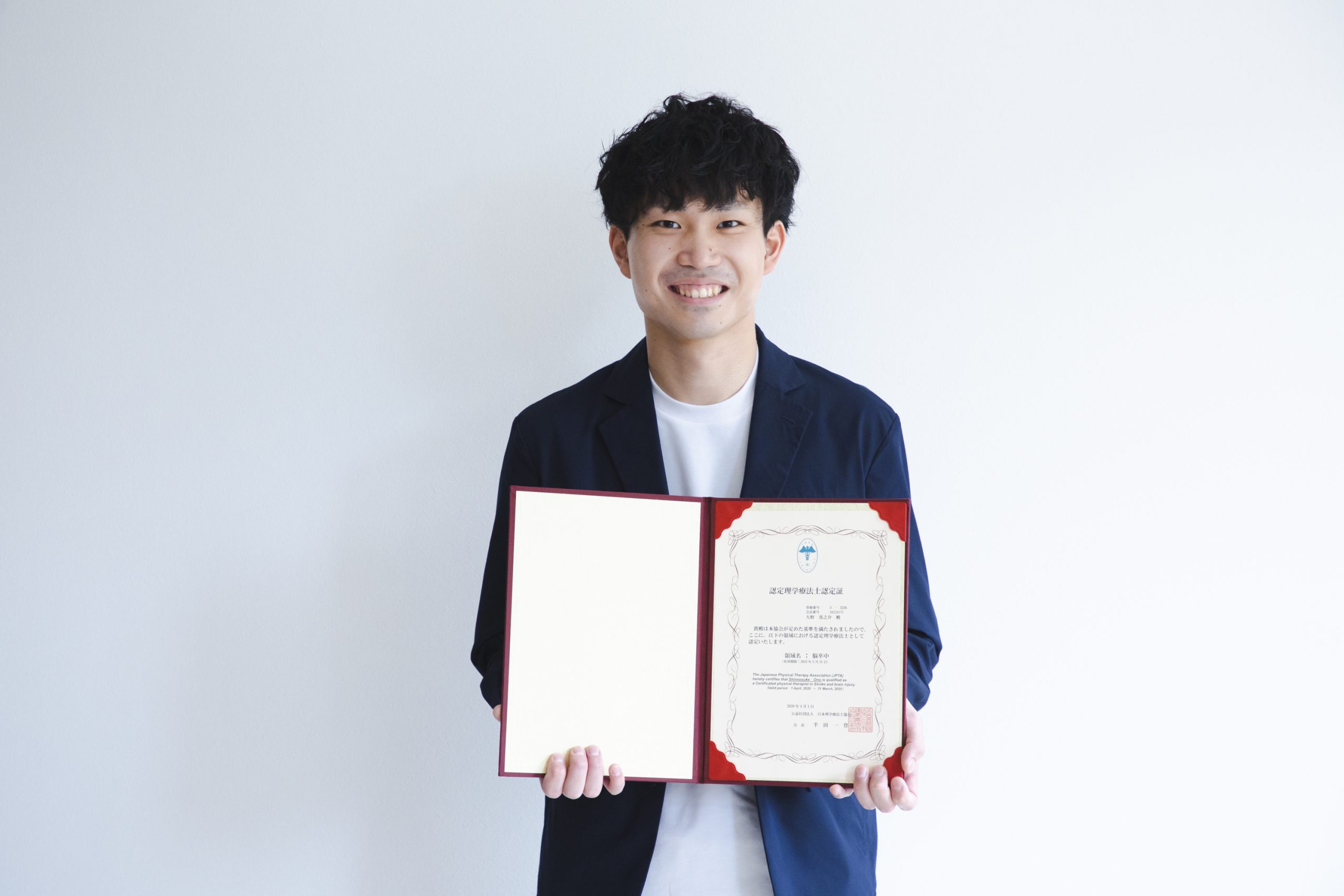
大野 真之介
理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中)
2016年に理学療法士免許を取得。同年より愛知県内の大学病院で勤務し、回復期・急性期・外来のリハビリを経験。急性期ではSCU(脳卒中集中治療室)の専任理学療法士としても勤務。
これまで主に脳血管疾患・脊髄損傷・神経難病の方のリハビリに携わる。2020年に日本理学療法士協会の認定資格である認定理学療法士(脳卒中)を取得。2022年11月から脳神経リハビリセンター名古屋に勤務。
私は常に「一緒に進めるリハビリ」を心がけています。療法士がリハビリをするのではなく、お客様にも“動き方”や“変化”を知ってもらいながら、運動を通して目標達成を目指しています。目標に向けて一緒に挑戦していきましょう。全力でサポートします。





